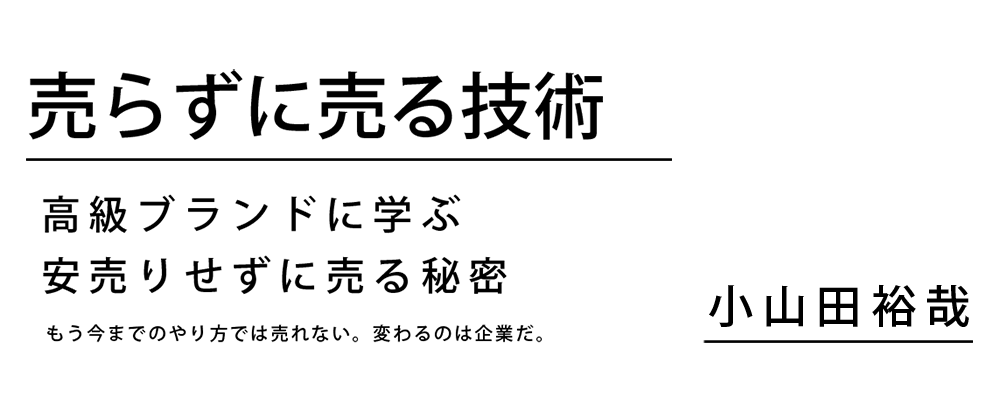書評 - BOOK REVIEW -
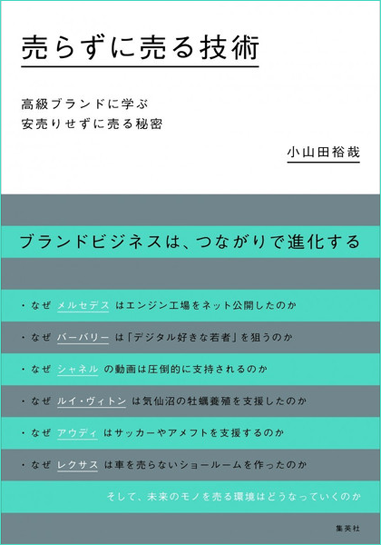
「若者の車離れ」、これは日本に限ることではなく先進国共通で起きている現象です。CNNの2012年の記事によれば、アメリカでは18歳から34歳までの新車を購入する割合が2007年から5年間の間で30%落ち込んでいるといいます。
以前は通過儀礼のように当たり前だった「自動車を買う」という習慣。それは、もはや当たり前ではなくなっているようです。現在、高級車の販売台数は世界的に上昇し続けていますが、これは「今現在」の話であり、若者がこのまま車に触れない生活に慣れてしまうと、いずれ市場は縮小していくだけになります。
■高級車メーカーは若者に何をアプローチしたのか
ショールームで待っていても誰も来ず、テレビでCMを流してもスルーされてしまう。車という「モノ」に興味がない若者たちに、どう魅力を伝えていくのか。
『売らずに売る技術』(小山田裕哉/著、集英社/刊)の中から一つ事例を挙げましょう。
創業100年を超える老舗メーカー、アウディのプロモーション戦略は一貫したものが見えるといいます。例えばスポーツの支援。ヨーロッパのビッグクラブといわれるレアル・マドリードやFCバルセロナ、ACミラン、バイエルン・ミュンヘン、ハンブルガーSVなどとパートナーシップを結び、世界中のサッカーファンにアプローチを仕掛けます。
アウディがサッカーを支援するのは、フォーメーションや作戦が多彩で、「知的なスポーツ」という面があるからだ、と小山田さんは言います。「知的なスポーツ」を支援することは、「知的なブランド」というイメージを与えることにつながると判断しているのです。
また、人口の上位2%の知能指数を有する人のみが入会できる「MENSA」の日本支部が作成した暗号を利用したプロモーションや、宇宙と関連したプロモーションなども展開。こうした姿勢は、車そのものを広告でアピールしても届かない人々に、「知的好奇心の刺激」というキーワードで接点を持つことを可能とします。
こうしたアウディのプロモーションについて、雑誌『BRUTUS』編集長の西田善太氏は「特にレリヴァンシー(relevancy)が高い」と評しています。レリヴァンシーとは「関連性」のこと。つまりプロモーションのメッセージが、ユーザーに「自分ごと」として響くかどうかを表す言葉です。車そのものをアピールしても、離れてしまった人には関連性が低く感じられます。しかしメッセージを「知的好奇心の刺激」に絞ることで、サッカー、暗号パズル、宇宙など、知的な要素を感じさせる物事に興味がある人々とつながることができる。それがアウディの強さを支えているといいます。
■一方的な押し付けに人は左右されなくなった
この『売らずに売る技術』は、「DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー」WEB版で連載されていた「ラグジュアリーは変われるか?」を加筆修正し、まとめた一冊で、連載タイトルの通り、高級ブランドのプロモーション戦略について鋭く切り込んでいます。
経済が低迷し、財布の紐が固くなる一方。さらに、若年層の間にはもはや「お金を払わない」という文化が生まれていると訴える人もいます。テクノロジーの進化はめざましく、スマートフォン一つあれば多くのことが満たせてしまうようになりました。
つまり、それは今までと同じやり方をしていても通用しない時代の到来です。
一方的な押し付けではなく、企業自らユーザーに歩み寄り、ファン目線で情報を発信する。例えば企業ツイッターの中の人(運用者)が話題になることがありましたが、田端信太郎さんはソーシャルメディアの属人性を理解し、人間らしさを感じるコミュニケーションをすることの重要性を訴えます。ファッションブランドのバーバリーの“中の人”はこのユーザーと同じ目線を大切にし、これまでとは違った価値を届けながら、ファンを増やし続けているのです。
本書のタイトルにもなっている「売らずに売る」という言葉はまさに現代のプロモーション戦略においての大きなキーワードの一つなのかもしれません。商品を買わなくても行きたくなる店、ネットは販路ではなく「メディア」と捉える。どうしても買わせることに注力してしまうところを、発想を変えてアプローチする。そうすれば、安売りをせずとも、ファンは増えていくのです。
豊富な企業の事例から、プロモーションの「今」を見つめることができる一冊です。
(新刊JP編集部)