人間心理を徹底的に考え抜いた
「強い会社」に変わる仕組み
著者:松岡 保昌
出版:日本実業出版社
価格:1,870円(税込)
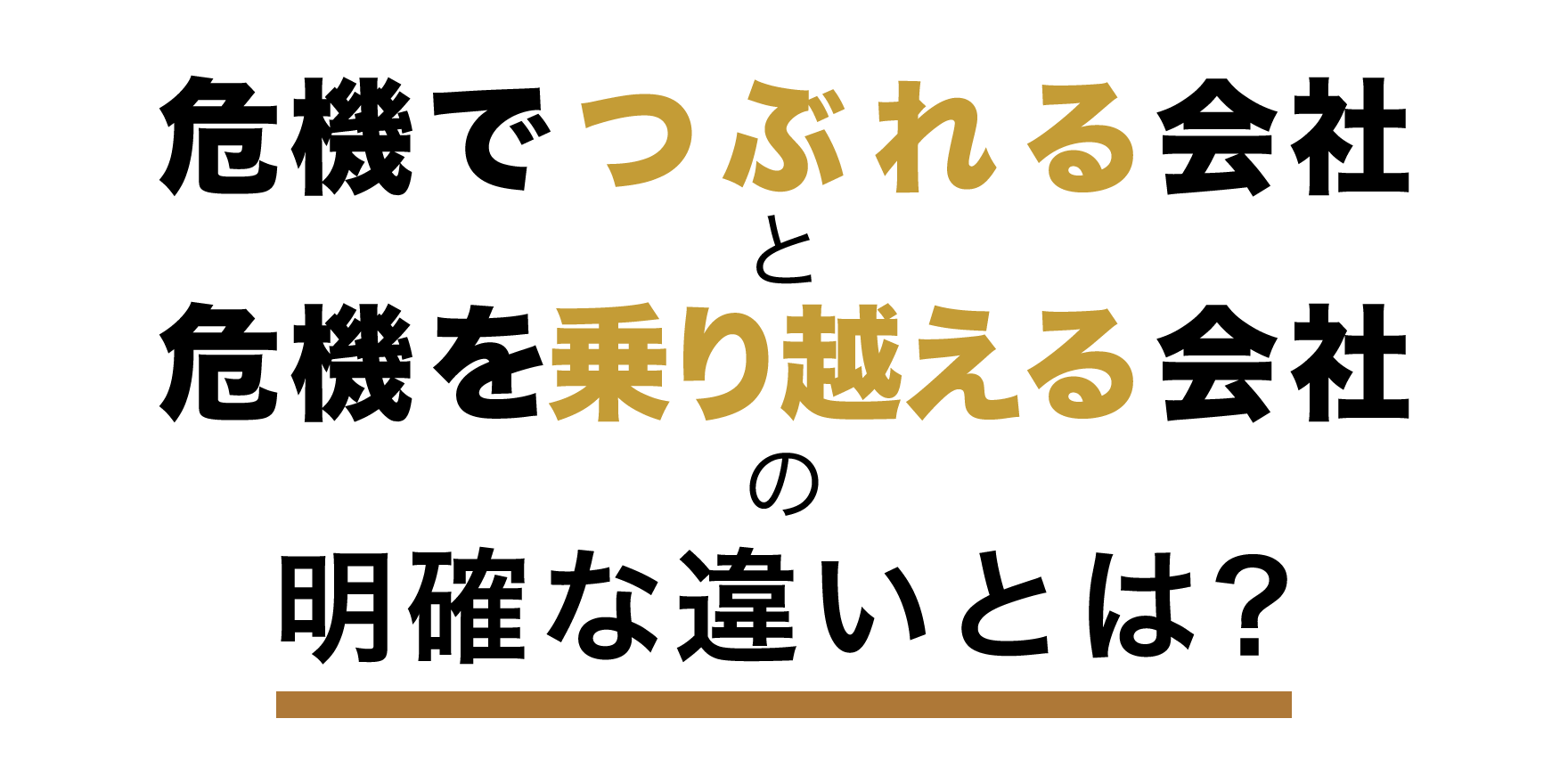
著者:松岡 保昌
出版:日本実業出版社
価格:1,870円(税込)
リクルート、ファーストリテイリング、ソフトバンク。
この3つの日本を代表する企業は、多くの会社の「お手本」とされる存在だ。それぞれのマネジメントや仕組み・制度、フレームワークを解説する本も数多く出版されている。
会社が危機に瀕したとき、まずは成功している企業のやり方を学び、それを取り入れるという手段は定石と考えるかもしれない。しかし、単純に他社の成功事例を取り入れても、自社と合わなかったり、うまく機能しなかったりすることも多い。そもそも冒頭にあげた3社でさえ「さまざまな危機を乗り越えて成長し続けている」という共通点はあるが、3社を解剖すると、業態もビジネスモデルも、そして内部のマネジメントの方法もそれぞれ異なることがわかる。では、まずそれぞれどのような特徴があるのだろうか?
たとえば、リクルートはそれぞれの課を「プロフィット・センター」と見なし、活動の自由度を高め、利益にコミットさせている。各プロフィット・センターが利益を出せば、リクルート全体の利益があがるという考え方だ。
一方、ファーストリテイリングは、製造から販売までを一貫して行う「製造小売業」で、組織一体になることが求められる。また、利益率の高いビジネスを展開できるが、売れ残りがあると大打撃となるハイリスク・ハイリターンのビジネスでもある。
最後のソフトバンクは、孫正義氏のトップダウンというイメージが強いが、実際は、孫氏と主要幹部クラスとのブレストで戦略を決めているという。「他人の脳を自分のものにする」といったところだろう。また、社員がソフトバンクのビジョンに強くコミットしているのも特徴だ。
このように、企業文化もマネジメントの方法も三者三様なのだ。
ゆえに、たとえばリクルートに近いマネジメントをしている企業が、ファーストリテイリング的な「仕組み・制度・施策」を学んで取り入れ、組織変革を起こそうとしても、まったく合わないということが起こりえる。
では、危機を乗り越えるために組織を変えるには、いったい何が必要なのか。
その答えが『人間心理を徹底的に考え抜いた「強い会社」に変わる仕組み』(松岡保昌著、日本実業出版社刊)に書かれている。
本書はリクルート、ファーストリテイリング、ソフトバンクを渡り歩いた著者・松岡保昌氏が、3社での経験や事例をふんだんに織り交ぜながら、あらゆる企業が組織を変革していくために何が必要なのかを解説する多くの示唆に富む一冊だ。「起業を目指すビジネスパーソンが今、読んでおくべき8選」で取り上げられたり、Amazonのユーザーレビュー数77、星平均4.3(1月28日現在)と高い評価を得ている。
私たちは、会社を変革しようとするときに「仕組み・制度・施策」の導入や変更から入ろうとする。それ自体は間違っていないが、えてして、そのときに話題になっている他社の成功事例を取り入れようとしがちである。
しかし、それではうまくいかない。それはなぜか。その会社のめざす「企業理念」、強みとなる「コア・コンピタンス」の視点が欠けているからである。松岡氏はこう指摘する。
組織戦略がうまくいくには、少なくともその会社がめざす「企業理念」が明示され、その会社の強みとなる「コア・コンピタンス」が発揮され、それを強化するための「仕組み・制度・施策」が導入され、機能していなければならない。(p.31より)
本書から、自社の「コア・コンピタンス」を見誤って失敗した事例を紹介しよう。
松岡氏がかつてコンサルティングで関わった地方都市を中心に展開する携帯電話の販売会社のケースだ。松岡氏よりも以前に入っていたコンサルティング会社によって、その携帯電話の販売会社には、優れた人事制度が導入されていた。一般によくある業績向上の視点だけではなく、企業理念をも実現させようとする評価指標が設定されていたのだ。しかし松岡氏は、その評価指標の一部に違和感を抱いた。評価指標で「効率性」が重要視されていたからだ。
携帯電話の販売会社にとって顧客数と売上は密接に関わるため、「効率性」は重要な指標だ。しかし、この会社にとってはその指標を重視することが裏目に出てしまい、景気が厳しくなったタイミングで業績が悪化してしまったのだ。
なぜなら、この販売会社の顧客の中には、携帯電話へのリテラシーが低い高齢者も多かった。そのため、訪れた顧客1人ひとりに丁寧に教えることで顧客満足度を高め、顧客が新しい顧客を紹介する形で業績を伸ばしていた。しかし、導入された評価制度によって現場での効率性が過剰に重視され、自ら「強み」を潰してしまっていたのである。
そこで、松岡氏は一定の効率性は維持しながらも、顧客が友人や知人に紹介したくなるような行動をとった人が、より評価される仕組みへと変えた。
これこそ、まさに自社のコア・コンピタンスを見誤った形で制度が導入されたがゆえに起きた失敗とその改善例だ。人事の「仕組み・制度・施策」は、社員に企業理念の体現を促し、コア・コンピタンスを強化するようなものでなければならないのだ。
松岡氏が語る、組織変革の常道は、まず組織の現状を分析し、「良い企業文化」と「良くない企業文化」をあぶり出す。そして、「理想の企業文化」をイメージし、その理想に辿り着くまでの課題を洗い出し、それをさまざまな「仕組み・制度・施策」へと昇華させ、1つひとつ実施していくことだという。
とりわけ危機を乗り越え成長し続けるためには、時々の状況を打破するための「理想の企業文化」をイメージできることが重要だ。「理想の企業文化」は、企業理念を実現し、コア・コンピタンスを研ぎ澄ますためには、社員がどんな考え方を持ち、どんな行動をすることなのかを考え抜くことで見えてくるという。
その理想を社員と共有し、社員一人ひとりが求められる考え方や行動の必要性を納得した時、企業はひとつの方向へと動き始める。その流れを促進させるものこそが、人事の「仕組み・制度・施策」なのだ。この理想の設定と共有ができるかどうかが、危機に対応できる企業と対応できない企業の分かれ道となる。
本書を読むと、マネジメントの形がまるで違うリクルート、ファーストリテイリング、ソフトバンクの3社においても、危機を乗り越え、成長し続けるための共通項があることに気づくだろう。その一つは、危機に直面した時の、それを乗り越えるための社員の本気度だ。どの企業にも求められる社員を本気にさせる仕組み、人が自ら動き出す企業文化になるための道筋が示されている。
また、この他にも「コミュニケーションは会社の強さを支える陰の主役」として、コミュニケーションの重要性、そして会議の効果を高めるための方法についても触れられている。実際に、リクルート、ファーストリテイリング、ソフトバンクという3社の事例を見ても三者三様で、会議で何を重視しているのかが異なる点が面白い。ここで紹介されている会議のコツは、オンライン会議においても活用したい内容だ。
◇
組織が硬直してしまうと、コロナ禍のような社会的な危機にも、社内で起きたクリティカルな問題にも対応できなくなってしまう。常に成長し続ける組織に変革するためには何が必要なのか。本書はその答えと方法を提示してくれる1冊である。
(新刊JP編集部)

■他社の成功事例を真似してもうまくいかない理由
松岡: 3つあります。まず、1つめについてです。人と組織について書かれた本については、理論についても、実話についてもたくさん出ていますが、理論か実話、どちらかに寄ってしまっていることが多いんですね。すると、理論の本を読んで理解はするけど、自分事、会社事として具体的にどう動けばいいか分からない、実話の本を読んで真似をしてみるけれど上手くいかない、ということが起こります。
理論を理解することも、実話を知ることも悪いことではありませんが、そこで一番足りない視点は「自社は何をすべきなのか」ということなんです。自社の現状の中で何をすべきかという視点がなければ、どんなに良い情報も活かすことができません。だから、その視点を伝えたいというのが、本書を執筆した動機の一つめです。
2つめの動機は、実際に組織変革を進めようと思っても、どうやったらいいのかイメージできない人が多いので、徹底的に会社を変えるところまでをイメージできるような情報を伝えることができないかということです。
そして3つめは、組織人事の問題で一番大事なのは「人の気持ち」です。そこを抜かして仕組みを取り入れようとする人が多いのですが、ヒト・モノ・カネの中でお金とモノは意図通りに使うことができても、人だけは意図通りにはいかない。モチベーションの高い集団と低い集団では、同じ人数でもパフォーマンスが大きく異なります。だから、人の気持ちが重要である、と。そこもすごく伝えたかったですね。
松岡: そういうことはよく起きていますし、失敗してしまうんですよね。それはやはり自社のコア・コンピタンスを無視してしまったり、理念をしっかり振り返っていなかったりすることに起因します。
もちろん、良いものはどんどん取り入れるべきですが、もっと大事なものがあるという視点が必要で、その例としてこの本の最初に、携帯電話販売会社が自社の強みを振り返らずに効率を優先した結果、顧客が離れていくというエピソードを書かせていただきました。
松岡: そうです。また、理論や実話に寄っている本の内容の受け取り方としてまずいのは、他社で成功をしたから絶対に良いやり方だと考えてしまうことです。もちろん、その成功事例に罪はありませんし、実際にそのやり方で成功した会社もあるのは事実です。だから本になるわけですよね。
でも、それがどんな会社にも共通する成功事例であるかどうかはわかりません。意図した結果にならないケースもありますし、逆に会社がおかしくなることすらあるのです
松岡: いえ、そういうわけでもありません。その他社の成功事例は、自社の企業理念を実現し、事業の中核的強みであるコア・コンピタンスを強化する方向に向かうのか、まさに自社に合うかという視点で見て、それに合わせる形で導入することができれば、成功の精度は高まります。

■危機を乗り越えて成長する強い企業が持っている共通点とは?
松岡: おっしゃる通り、ビジネスモデルも社風も全く違う3社でした。もちろん、そこに良し悪しはありません。それを前提にお話をしますと、私がいた頃のリクルートは個人の力の集合体のような会社でした。ベースに個人の自由がありました。これは当時社長だった江副浩正さんが「多くのリーダーシップ論では、1匹のライオンが100匹の羊を操る術が説かれているが、私はライオンになれないので、100匹のライオンを束ねる羊なろうと思った。そういうやり方があってもいいのではないか」というコンセプト通りです。
次に勤めたファーストリテイリングは、首尾一貫して、いかに組織全体が機能的に動くかが大事な会社でした。その意味ではリクルートと全く逆ですね。でもそれはビジネスモデルと嚙み合っていて、逆にそれが実現できなければ成長はないという状況でした。
ソフトバンクは何をすべきかを決めるときに徹底的にブレインストーミングをするんです。そして決めたことは徹底してやり抜く力がある。つまり、他人の脳みそまで使って何をやるべきかを決断する力と、やり抜く力の両方があるということですね。PDCAのスピードも速くて、大企業では1、2週間かかることをソフトバンクでは1日、2日でやり遂げてしまう。それくらいの差がありましたね。
松岡: それが後ほどお話しようと思っている共通点に通じてくるのですが、当時のファーストリテイリングはビジネスモデルを「製造小売り」に転換している時期で、伸び悩んでいたんです。ただ、経営トップの柳井正さんは、まず日本一、そして世界一になりたい、アパレルの世界を変えるのだと言っていました。私はその趣旨に賛同したので、どうやったらそれが実現できる企業文化になるのかを実践したくて、ファーストリテイリングに移りました。
同じようにファーストリテイリングからソフトバンクに移ったときも、同じように経営トップの孫正義さんの趣旨に賛同して移りました。社風やビジネスモデルというよりは、企業として何を目指しているのかがしっかりしていたため、コミットメントできたと思います。
松岡: 経営層への信頼というよりは、世の中に提供する価値を表す「社外規範」への共鳴というニュアンスが強いです。世の中を変えていく集団の中に自分も参画しているという感覚ですね。リクルートやファーストリテイリングでもそうでした。自分たちが世の中に影響を与えて、社会を変えているという実感を持つことができれば、気概もアドレナリンも出てきます。
松岡: PDCAのサイクルのスピードが強烈に速いことですね。リクルートには「なぜそう思っているのにすぐ言わない、なぜやらないんだ。すぐにやれ」という文化がありますし、ユニクロは即断即決即実行を大事にしています。「52週のマーケティング」にしても、愚直に週末までの売上を月曜日の朝確認して、すぐに次の土日の売上のための手を打っていくという、PDCAのサイクルができていました。
ソフトバンクも毎日のようにシミュレーションをして、ABテストなども日々重ねていく。それはウェブ関連だけでなく、営業電話の仕方ひとつ取ってもそう。どっちのやり方が響くのかデータを取って良い方法を選択していきます。
松岡: もちろん、違います。ビジネスモデルが違いますから。ただ、スピードが速いという共通点はあります。それというのも、自社に合った仕組みを取り入れているから、それが達成できるわけですよね。
松岡: 3社の危機を具体例で説明すると、リクルートでは1988年にリクルート事件が起きました。あれほどの教科書にも載るような事件を起こした会社で、現在も成長し続けている会社はなかなかないと思います。私も当時社内にいましたが、ものすごく世間から叩かれましたね。
ユニクロも2000年、2001年と毎年売上を倍増させるほど伸びたのですが、その直後、逆風が吹いて急激に売上が下がってしまいました。でも、その危機を乗り越えて成長を続けています。
ソフトバンクは危機というわけではないのですが、積極的投資を進めて1000億円近い赤字を3年出し続けたことがあります。Yahoo!BBを始めた頃ですね。私が入社する前の話ですが、全社的な緊張感は高かったようです。でも、それを徹底してやり抜いたのが、ソフトバンクの力なんですよね。
こうした経験を通して言えることは、まずは日頃から「理念」を共有ができているかどうかがすごく重要だということです。リクルート事件のときは電話をかければすぐに切られるし、飛び込み訪問したら塩を撒かれるくらいの勢いで拒絶されました。そんな中で私たちが考えていたことは、社名は関係なく自分たちの事業はどんなことがあっても残すということでした。それは自分たちがやっていることは、絶対に社会のためになるという覚悟があったからです。
松岡: そうです。自分たちが事業を通して成し遂げようとしていることに本気になっている。だからこそ、会社は危機を乗り越えられたのだと思います。逆に言えば、会社の看板がなくても仕事をするぞという覚悟です。
また、「社外規範」への共鳴とともに、社内で理想とされる行動や考え方、つまり行動指針である「社内規範」への共鳴もありました。リクルートの社内規範である「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という働き方に共鳴していたんですよね。
これは、ファーストリテイリングもソフトバンクも同じでした。世の中を変えるという社外規範があって、そこにコミットメントしている。だから危機を乗り越える共通ポイントは何かというと、「社外規範」と「社内規範」への共鳴が大きな1つとしてあげられます。
松岡: これも大事なポイントですが、上司が「理念」に則った会話や対話をしているかという視点が重要です。コミュニケーションの中で根付かせることが必要なんです。たとえば、理念で「顧客のため」と言いつつも、部下が営業先から会社に戻ってきたときに、上司が「売上は? 契約は取れたのか?」だけを聞いたら、極端な言い方ですが「騙してでも契約を取ってこい」というニュアンスになりますよね。
松岡: でも、同時に上司が「お客さんは喜んでくださったか? 提案に驚いてくださったか?」と聞くと、顧客が大事だと皆が思うでしょう。だから企業理念と重なる価値観を上司が普段から問いかけているか、社員に求めているかというのは、社内の会話でわかるんです。日常の会話を聞けば、何を大事にしているかがよくわかる。
松岡: おっしゃる通りです。トップだけがメッセージを発していてもなかなか浸透はしません。幹部全体もそのメッセージを発信し、さらにその下のマネージャーに浸透させていく。上から順に腹落ちさせていくということは、すごく重要です。
その時に鍵を握るのは、幹部やマネジャーの価値観が一枚岩になっているかどうかですね。例えば、岐路に立った時に右にも左にも行けるけれど、うちの会社は右を選択するよね、という価値観を共通して持っていると、会社はすごく強くなります。

■「人が自ら動き出す」強い組織はどのようにして作られるのか?
松岡: そうですね。変わりたくない人はもちろんいて、それが経営層や幹部層にいるとさらに厄介です。自分の反対意見に賛同する人たちを集めて、社長に直訴することもあり、そこで社長がブレてしまうと改革は立ち行かなくなります。
ただし、もし抵抗勢力が生まれても、すぐに彼らを敵視してはいけません。まずはオープンに議論をしましょう。「なぜ、変わらなければいけないのか」を伝え続けることで、やがて賛同してくれるようになることも多いです。
松岡: すぐに排除しようとしてはいけません。変わりたくないのはむしろ人の本性。その人たちの気持ちをいかに動かすかが問われるのです。もちろん周囲に負の影響が出ないような工夫は必要です。うまく変革を進めるためにシナリオを描くことが重要です。例えば、影響力のありそうな人から巻き込んで良い方向に向かわせるというのも1つの方法です。
松岡: 私の考えとしては、変わる方向に努力をしてくれる人は、みんな組織の中にいていい人たちだと思います。もちろん変化にすぐに対応できる人、そうではない人と分かれると思いますが、変わるために努力をしてくれているという事実が一番大事なんです。
人の成長って面白くて、直線的ではないんです。最初はすごく苦しんだけれど、あるふとした瞬間に一気に成長することが普通にあります。いわば「覚醒する」みたいな感じです。変われなかった人も、どこかで腹落ちすれば急に動きが良くなったりするんです。
松岡: 理解して変わろうとしてくれる人たちは大事な人たちです。もともと変化への対応に得意な人もいれば、苦手な人もいます。ただ、その方向を向いて努力する人ならば、待ってあげてもいいのではないかと思います。
松岡: これはいろんな言い方ができますね。主体性を発揮すること、当事者意識を持つこと、他責にしないこと。もう少し長い言い方をすると、課題を認識して、そのために何をすることが自分の役割なのかを自分で考えて行動するようになることです。
少し前に「ティール組織」が話題になりましたが、まさにこのことなんですね。みんなそれぞれ考えて動けるから、指示命令はいらないという話なんです。ゆくゆくはそうなるのが理想ではありますが、そこに至るプロセスは必要で、1人ひとりの当事者意識が高まらないと難しいでしょう。本書はそれに必要なことを「特別付録」として書き綴りました。
松岡: そうです。心理学の中でもとくに経営のために知っておいたほうがよい知識から、フォロワーシップ、チェンジマネジメントなど、リアルで応用できることを書いています。
松岡: 組織変革にゴールは存在しません。なぜなら、外部環境は常に変化しているからです。外部の環境に合わせながら、常に自社の理念を追い続け、コア・コンピタンスを研ぎ澄ましていく。そうするにはどうすればいいかを常に考え直していくことが重要なんです。
たとえば、コロナ禍をきっかけに、新しい実情に合わせて人事評価制度を変えてもいいんですよ。それも、目指している理念に合うものであればです。外部環境が変わるのに、制度だけ昔のまま取り残されていくことのほうが実は危ないです。会社の硬直化はそういうところから始まります。
松岡: 前半でも少し述べましたが、現場の日常会話からも出ますね。たとえば、それまでは他部署に対して「こうしたほうがいいんじゃない。こうしてくださいよ」というアドバイス的なニュアンスや自分たちの責任ではないという前提で発せられていた言葉が、「こうしましょう」というように自発的に取り組もうとする語尾に変化します。
もう1つは、発言の視点が「全社視点」になります。普通は部署視点での発言が多いのですが、たとえばコロナ禍後を見据えて新しいビジネスモデルを見つけなければならない時などは典型ですが、1人ひとりが全社最適の視点で考えるようになるんです。それが現場レベルで起きてくる。部署間の壁を越えて「大変だけど会社のために一緒にやりましょう」と。こうなってくるとかなり変わってきていますね。
本書の5章では「コミュニケーションの仕組み」について触れていますが、まさに変化を促すのも、発見できるのも、そこなんです。会議のやり方一つでも変わってきますからね。
松岡: そうなんです。

■コロナショックの危機を乗り越えていくために必要なこと
松岡: シナリオ力とは、ゴールまでの道筋やマイルストーンを常にイメージできるかどうかの力ですね。もちろん、シナリオ通りに進むことはまずないですから、途中で変化を余儀なくされても、すぐにまたゴールまでの新しいシナリオを考えられるかどうかということで、その力です。
松岡: リーダーだけではありません。自分がやるべき仕事をやり遂げるためのシナリオなので、あらゆる人に必要です。
人を巻き込まないとゴールにいけない場合には、どのタイミングで誰を巻き込むか、そしてどのように巻き込むかを、相手の気持ちを考えながら決めていきます。たとえば、人事部長や経営企画室長として会社の企業文化を変えようと考えたときに、まずはトップにその必要性をどう認識させどう巻き込むか、その下の現場マネージャーをどう巻き込むか、その一連の流れをイメージするんです。
ただ、人の気持ちを考えずに「これやってください」だけだと、相手に当事者意識が芽生えませんから、うまくいきません。いかに相手に当事者意識を持ってもらいながら巻き込んでいくか、それができるかできないかで大きく違いますね。
松岡: まずは経営者。これはトップだけではなく、役員幹部を含めた何らかの形で会社や組織を運営している人たちと、それを目指している人たちです。そういう方々にとっては参考になるはずです。
もう1つは人事の方々ですね。人事の方々は自分の仕事の役割を狭く考えているケースが多いのですが、実は広いんですよ。会社がうまくいくための雰囲気作りや企業文化を作って強い集団にするのも人事の大事な役割です。そういう方々にも参考になることが書かれています。
松岡: 1つは、抽象度を上げて言いますと、危機は社員の本気度を今一度高める時だということです。自分たちの大事にしているもの、目指しているもの。この本で言うところの「社外規範」ですね。自分たちは世の中で何を成し遂げたいのか、どんな価値を残したいのか、そのために自分たちはどんな動き方をするのかというあたりを、もう一度全員で再認識することが重要です。
では、そのためにどうすればいいのか。方法が3つあります。1つはすでに実績のある会社であれば、今までお客さんに喜ばれたこと、自分たちが成し遂げてきた価値があるはずですよね。その価値をもう一度思い出せるようにすることです。
それには社内に向けてのアピールが大事で、社内報や会議でのトップのメッセージを最大限活かしましょう。そして、どの会社でもできることではありませんが、極端なことを言えばテレビCMを使って社員に伝えるという方法もります。日産はまさにそれをやったわけです。木村拓哉さんが登場する新しいCMシリーズの最初のものでは、今まで自分たちが世の中に出してきた価値を、テレビCMという形で顧客にも社員にも思い出させていたのだと思います。そういう仕掛けも必要なんです。
2つめは「外からの声」を中に届ける工夫をすることです。顧客含めた外部からの良い評価を知ることで、自分たちの会社や仕事が社会の中で必要とされていることを再認識できるんです。存在価値があることを確信できたら頑張れますよね。自分たちが本気で取り組むべきことを、もう一回腹落ちさせることができる。
飲食店なら、お店の中で食べてもらう業態からテイクアウトに変わったかもしれないけれど、根っこは一緒。美味しいものを食べて幸せになってほしいという、その意識を再認識してもらう、というような形です。
3つめは、ヒーローづくりです。変化に対応するためには、「既存の仕事のやり方」から「新しい仕事のやり方」に変わらなければいけません。そこで新規事業などもそうですが、日常的なことでも「新しい仕事のやり方」を生み出した人にスポットライトを当てるのです。その良い動き方をしてくれた人をヒーローにすることが大事なのです。そうすると、多くの人がその人を真似て、新しいやり方を生み出すことに挑戦してくれますよね。その雰囲気作りが重要です。
この3つを前提としたうえで、さらに大事なことが2つあります。まずは、仕事を硬直化させずに新しいアイデアを1人ひとりが生み出していけないといけません。商品開発にしても、事業を変えるにしてもです。そのためには、フランクに話し合える環境が必要です。つまり、心理的安全性が保たれたうえでのブレインストーミングができる会社かどうかがすごく重要です。ブレインストーミングという言葉自体は、何年も前から浸透していますが、実際にできている会社は少ないです。
もう1つはそれぞれやると決めたとき、「自由」と「規律」をもってPDCAを回すことです。「自由」に意見を言い合える環境とともに、とにかくやらないといけない時には「規律」をもって全員が徹底的に取り組めるかどうかです。この5つがそろうと、大きな変化にも対応できると思います。
松岡: そうですね。リクルート事件で窮地に立たされたリクルートは、まさにそうやって危機を乗り越えていきました。社風や企業文化が違っていても、このやり方は共通すると思います。
(了)


松岡 保昌(まつおか・やすまさ)
株式会社モチベーションジャパン代表取締役社長。人間心理にもとづく経営戦略、組織戦略の専門家。1963年生まれ。1986年同志社大学経済学部卒業後、リクルートに入社。『就職ジャーナル』『works』の編集や組織人事コンサルタントとして活躍。2000年にファーストリテイリングにて、執行役員人事総務部長として当時の急成長を人事戦略面から支える。その後、執行役員マーケティング&コミュニケーション部長として逆風下での広報・宣伝の在り方を見直し新たな企業ブランドづくりに取り組む。2004年にソフトバンクに移り、ブランド戦略室長としてCIを実施。福岡ソフトバンクホークスマーケティング代表取締役、福岡ソフトバンクホークス取締役として球団の立ち上げを行う。また、AFPBB News編集長として、インターネットでの新しいニュースコミュニティサイトを立ち上げる。現在は、株式会社モチベーションジャパンを設立し、代表取締役社長として、企業の成長を経営戦略、組織戦略、マーケティング戦略から支える。筑波大学大学院 人間総合科学研究科 生涯発達専攻カウンセリングコース主催「キャリア・プロフェッショナル養成講座」修了。国家資格1級キャリアコンサルティング技能士、キャリアカウンセリング協会認定スーパーバイザーとして、個人のキャリア支援や企業内キャリアコンサルティングの普及にも力を入れている。
会社HP https://motivationjapan.co.jp/
著者:松岡 保昌
出版:日本実業出版社
価格:1,870円(税込)