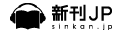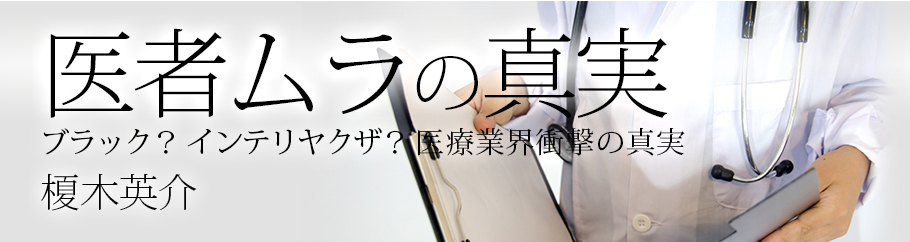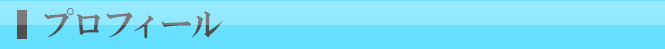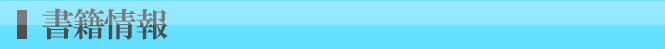―まず、医療業界の現場で起きていることについて、とても正直に書かれている印象を受けました。本書内でも書かれている通り、近年、医者が業界を告発する本を出してはベストセラーになるということが起きている中で、本書を執筆した理由からお聞かせ願えないでしょうか。
「おっしゃるように、本書はかなり率直に医者や医療業界が抱える問題を書いています。一見、医療業界の暴露本のようにみえるかも知れません。けれど、それは真意ではありません。
本書を執筆した動機は、自分が今いる医療の世界が、いろいろな意味でなんかおかしいぞ、と思ったからです。
私は、もともとは理学部の大学院にいましたが、中退して医学部に学士編入学しました。家族には医者はいません。医学部在学中は研究をしていて、32歳で卒業後は臨床研修をへて病理医になりました。この病理医というのが、全然普通の人に知られていない。医者からも「それって医者の仕事?」と言われるほどに知られていません。それぐらいマイナーな「めずらし医」です(苦笑)。
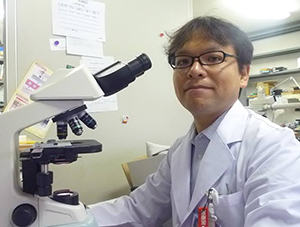
そんな異端な立場からみると、医者や医療業界というのは、なんか変だ、ということが多いです。病理医は絶滅危惧種なみにいないし、医学部の研究現場には医者がいません。結構危機的なのですが、あまり報道もされませんよね。これは誰かが訴えないといけない、と思い、本を書くことにしました。
一方で、医者の子弟がびっくりするくらい多い医学部の学生とか、製薬メーカーがスポンサーの、弁当つきのセミナーとか、医局とか、外の世界から来たら「なんだこりゃ?」と驚くようなことが、当たり前になっています。まあ、どんな世界も業界のルールみたいなものはあるわけですけど、医者の場合、人々の健康をまもるという、ある種公的な職業ですよね。そんな職業が、内輪のルールにだけ従っていていいのか、という疑問も感じていました。だから、そうした内輪の世界、それを「医者ムラ」と言ったわけですが、医療業界の問題点を解決するきっかけになればと思ってムラの内実を明らかにしたわけです。
ただ、それは最近はやりの「医療否定」、医療は患者さんに害を与える、医療は不要であるという本と一緒にされたくはないという思いもあります。こういう本は売れますよね。近藤誠先生の本が代表ですが、確かにそういう本は、非常に分かりやすくて、これはこうだ、と断言するので、読んでいて痛快です。こういう本が読者を獲得するのはよく分かります。そういう本が指摘する問題、たとえば過剰な治療が患者さんに害を与えているケースがある、というのは、医者の中にも賛同する人が多いと思います。
しかし、そうやって、これはだめ、あれはダメ、医療はだめ、と断言することは、医療の問題の解決になるのかなあと疑問に思ってます。
確かに、一部の患者さんにとって、こうした「直言」に従うことで、症状が良くなることがあるでしょう。しかし、すべての患者さんがこれで救われるとは思えません。
私の親しい人には、乳がんを放置したために、若くして亡くなった人がいます。私の父も、心臓の血管が詰まっていたのに、治療を放置したために突然死しました。
私がこの本を書いた理由の1つは、現実は一言で表現できるほど単純ではないということです。当たり前と言えば当たり前なのですが、世の中は複雑に入り組んでいて、利害が対立したり、見解が異なったりすることが多いわけです。そうした中で、合意を得るのは大変だし、めんどうくさい。だから、ワンフレーズで「医療はダメだ」という人の声を聞きたくなってしまう。
けれど、そうした面倒くささをすっ飛ばして、極論だけ叫んでいても、医療の問題点は変わりません。
だから、私はこの本で、医療の問題点を挙げつつ、それを対話や議論で解決すべきと訴えています。たとえ面倒くさくても、手間でも、それ以外道はないと思います。医療が抱える問題を解決するのに魔法の杖はないのです。」
―医師がブラック企業並の勤務実態であることは知られていることですが、改めてこの本でその苛酷さを理解しました。特に近年は社会からの要求やモンスター患者などの登場によって、勤務時間以上の精神的負担が増えていると思うのですが、そういった感覚はありますか?
「はい。医者、とくに勤務医の過剰労働はおそらく昔からあったと思うのですが、まだ昔はましだったと思います。というのも、まだ患者さんから「ありがとう」と言われる機会が多かったからです。
ところが、近年は、医者は病気を治して当たり前、治せなかったらクレーム、訴訟、というケースが増えているように思います。
ミスではなく、起こりうる合併症でも訴えられるケースは増えています。産科医が逮捕されてしまった福島県の大野病院の事件は、その象徴です。どんな医者も、患者さんを傷つけようと思っていません。もちろん力至らなく、患者さんが亡くなることはあります。ミスすることもあります。もちろん、医療ミスなどは、調査の上医者が罰せられるべきこともあるでしょう。しかし、何かあれば犯罪者扱いされるということが、医者のやる気を著しく削いでいます。
こうしたことが積み重なり、今の医者たちは精神的に疲弊しています。過酷な勤務医を辞める医者もおり、医者不足が加速しています。それが残った医者にますます負担をかけるという悪循環に陥っています。」
―こうした勤務医の過酷な現状を打破する動きは、医療業界内にあるのですか?
「さすがにこうした過酷な現状にもう耐えられない、何とかしなければ、という声が医師のなかにも増えてきました。こうした医師たちが、現場から声をあげはじめています。
その1つは全国医師連盟です。全国各地の勤務医がインターネットを介して集まり、医師の過剰労働の問題をはじめとする様々な問題を社会に訴えています。全国医師ユニオンという、医師が個人で加盟できる労働組合もできました。医師は数年ごとに病院を異動するので、職場の労働組合に加盟していないことも多く、それが医師の労働環境改善を阻んできた側面があります。個人加盟の労働組合である全国医師ユニオンの誕生は、医師の労働問題を改善する上でとても重要だと思います。
―「医師」という職業は一つのステータスで、高収入であることから、婚活などで理想の職業の上位に来ることが多いのですが、こういう形で注目を浴びることに対して、何か感想はありますか?
「確かに、男性の医師はモテます。まあ、私なんかは対象外なんですけれど、世間からみたら、ある程度の収入があって、しかも失業の心配もないということで、安全パイというか、安定を考えるならいい相手なのでしょう。逆に女性の医師は、結婚相手としては敬遠されてしまうことも多いようで、婚活に苦労している人もいるようです。
けれど、医者と結婚してもあんまりいいことないですよ。何より忙しすぎるから、家事や育児など、家の仕事をしないし、看護師さんなど周りに若い女性がいるから、浮気や不倫もあったりする。あるとき、真夜中の手術室に執刀医の奥さんから電話がかかってきた場面に遭遇したことがあります。その執刀医が、手術と言って浮気したことがあったから、手術室にいることをわざわざ確認しているわけです。こんな家庭、壊れてますよね…
というわけで、結婚を人物ではなく、お金やステータスだけで判断することは、まったく賛同できませんが、こうした形で医者が注目をあびるのは、日本社会の問題ですよね…ほかの職業がもっと大変な状況だから、医者が相対的によく見えてしまうという…
だから、医者がモテるということは、日本の社会が停滞していることの裏返しなのかなと思って、心が痛みます。」
―学閥に関するお話は、まさに医療業界の中にいる人しか分からないことだと思いますが、ドラマで描かれているような病院内の権力抗争などは本当にあるのですか?
「言いにくいのですが、ある程度本当です。まあ、ドラマは誇張されていますけど、それに近いようなことはあります。本に書けなかったことも多いです。クビが飛んじゃうから(苦笑)。
さすがに怪文書などは読んだことないですけれど、タイミングのよい(?)時期にスキャンダルが明らかになったりとか。教授選のあとに医師が大量退職したなんて話は報道もされたりしていますよね。
基本的に医者のプライドは高いです。軽く見られたくないという気持ちは人一倍強い。だから、医者同士が争うと、プライドとプライドのぶつかり合いになって歯止めがかからなくなってしまう。そうなると、患者さんのことなどそっちのけです。
こうしたことは別に医者に限ったことではないですけれど、私はそこに、人間の生まれ持った本性を見てしまうんですよね…」
―榎木先生はかつて研究者を志していたけれど、才能がなくて断念し、医師の道を歩んできたと本書内で書かれています。研究者に求められる才能や素質とはどのようなものでしょうか。
「なんで私が研究者としてぱっとしなかったかというと、一つのことに執着できる根気というか、集中力が少し足りなかったからかなあと思ったりしています。あと、ちょっと思考がネガティブだった(苦笑)。
研究というのは、人が考えなかったことを思いついて、仮説をたて、それを何らかの方法で証明するということをするわけです。それは口で言うのはたやすいですが、ものすごく大変です。人が考えなかったことを思いつくことも大変ですが、思いついたとしても、それを証明する方法がなければダメなわけです。そして証明する方法がみつかったとしても、証明するまでには時間がかかりますし、証明できない場合もある。しかも、世界中の研究者がライバルです。競争に勝たなければならない。2位じゃだめなんです。
こうした状況を楽しめるような楽観的な人でないと、研究者として成功するのは難しいでしょうね。
あと、運もあります。というか、運の要素はものすごく大きい。たまたま人からやれと言われたテーマで研究したら大成功した、なんてことはゴロゴロあります。一人の成功者の周りには、失敗者の屍がやまのようにある。努力しないで成功する人はいませんが、努力したからと言って成功できるとは限りません。私も運は全然なかった(苦笑)。けれど、成果のでないまま40代で路頭に迷うということはありませんでした。こじらせないうちに方向転換をできたのは、今考えると良かったのかもしれません。」
―榎木先生がこれまで対峙してきた中で、これは理不尽だなとおもった出来事を教えて下さい。また、患者から言われて一番困ることはなんですか?
「私は病理医として、病理診断を行っているわけですが、患者さんと直接接することはほとんどありません。普段は他の科の医者相手に仕事をしています。だから、理不尽だな、と思う対象は他の科の医者だったりします。
理不尽だなと思うことは、他の科の医者が病理に対して無理難題を押し付けてくることですね。守秘義務があるので、具体的なことは言えませんが、診断すべき標本ができていないのに、今すぐ診断しろと言われたりとか、思っていた結果と違う診断結果が出たら怒鳴りこみにくるとか、他の科の医者に振り回されるときは、叫びたくなることがあります。誤診で迷惑を被ったからオレに謝罪しろと言われたこともあります。患者さんに謝罪するというのは分かりますが…
他の科の人たちにも言い分はあると思います。それは分かるのですが、チーム医療の一員として、お互いを尊重し、よく対話すればいいのにと思います。そうしたことができていない医療現場、医者の態度は大きな問題があると思います。
患者さんから言われて困ることですか…拙い臨床経験でいうと、こんなのですかね。例えば救急外来などでは、重症な人ほど静かで、軽症な人ほど大きな声が出せます。重症の患者さんを優先させるのは当然ですけれど、そんなときに軽症の人が、「オレを先に診ろ!」と騒ぐ現場に遭遇したことがあります。そういうのはものすごく困ります…
本書にも書きましたが、今の医療の現場では、「はやい」「うまい」「やすい」を両立することは難しくなってきています。すぐ診察してくれて、しかも一流の技術で、かつ安価で、ということですが、医者不足は深刻で、少ない医者でたくさんの患者さんをみるから、「はやい」を実現することが難しくなっています。「オレを診ろ!」と言われても無理です。そうした状態では医者のスキルアップも難しい。医者を増やすとなると、教育にお金がかかるわけで、「やすい」は実現できない。ジレンマです。
こうしたジレンマがあることを、読者の皆さんにも知ってもらい、そしてどうすればよいか考えてほしいと思います。」
―週刊誌や書籍などで「医療業界は腐敗している」と指摘されることもあると思います。そういった報道について、どのようにお考えですか?
「前にも言いましたが、確かに医療業界に問題は多いです。週刊誌や本が指摘することはあたっている部分も多いです。そうした問題点を明らかにして報道することは、メディアの重要な役割だと思います。
けれど、医者を全員取り替えることはできません。医療は一分、一秒たりとも止めることができないわけです。問題がある状態のままでやっていかないといけない部分があるわけです。
だから、報道に望むことは、糾弾というか、一方的に叩くだけでなく、じゃあどうするんだ、ということを含めて伝えてほしいということです。そうした良質の報道はたくさんあります。問題意識を持ったメディア関係の方々とは、是非いい意味での緊張関係を保っていけたらなと思います。」
―榎木先生が持っていらっしゃる理想的な医師像について教えて下さい。
「意外に思われる方が多いかもしれませんが、理想の医師は「普通の人」です。
え?どうして?と言われそうですけれど、普通というのはものすごく重要だと思っています。
今の医者は、ものすごく特殊な人たちです。医者一家か偏差値エリート、あるいは両方出身の人たちが多いわけです。もちろん、そういう人たちによいお医者さんはたくさんいるわけですが、医療が社会的な部分を切り捨てて、患者さんをある意味置いてきぼりにして技術優先になってしまったのは、そうした特殊な人たちが多いことと無関係ではないように思います。
患者さんがどんなところに住んでいて、どんな家族構成で、どんな経済状況なのか、そういうことも含めて考えていかないと、患者さんの立場にたった医療はできないと思います。残念ながら、今の医者は多様性がなくて、経済的に裕福な家庭出身の人が多いので、そういうことになかなか思い至れません。
そういう意味で、普通の家庭出身の医者ももっと増えてほしいのです。
もう一つの普通は、普通の人が働ける環境を作るために、問題を問題だとちゃんと言える人です。
医者は基本的に真面目で、コツコツとなんでもやってしまいます。受験勉強でそうした能力が鍛えられるためでしょう。だから、医療現場に問題があっても、なんとかこなしてしまう。寝ないで働いたりできてしまうのです。ある種超人です。
けれど、いくら個人の能力が高くても、過酷な勤務を長く続けることはできません。ある日燃え尽きてしまう。今医療現場で、突然燃え尽き、現場から立ち去る人が増えていると言われています。また、女性医師やイクメン医師は長時間労働ができず、現場からはじき出されます。
だから、そんな超人的な能力を医者に求めてはいけないのです。普通の体力でも働ける職場を作っていくべきだったのに、超人に頼ると、突然崩壊してしまうのです。
普通の人が働ける環境を作るために、医療現場から声をもっとあげていかなければなりません。声をあげられる普通の医師が増えてほしいと思います。」
―本書をどのような方に読んで欲しいとお考えですか?
「医療に関わるすべての人に読んでいただけたらと思います。世の中に医療機関にかからずに過ごせる人はごく小数なので、要はあらゆる人に読んでほしいです。
とはいうものの、結構分厚い本になってしまいました。歯ごたえは多少あるかも。政治や経済、社会問題に関心のある人には特におすすめします。
あと、医者にも読んでほしいですね。病理や研究のことなど、他の科の医者も知らないことですし。また、医者が当たり前と思っていることは結構社会からみるとおかしいことだよ、ということも知ってほしいですね。」
―このインタビューの読者の皆さまにメッセージをお願いします。
「本書は、ちょっと変わった経歴を持つ私の視点から、普段はなかなか取り上げられない問題を中心に、医療の問題をとりあげました。
すでに述べましたけれど、本書は暴露本ではありません。医療問題を取り上げるだけでなく、どうやったら解決するかということも述べさせていただきました。
結局、立場の異なる人が対話をして、解決策を考えていくしかないというのが結論です。医療に関わる人、それは、今は健康な方も含まれますが、あらゆる人が自分の立場を表明し、それをオープンな場で議論し、妥協ではなく、それぞれの立場の人たちが満足いく案を考えていくことしかないと思っています。「医療否定本」は劇薬でしかありません。

本来は否定的な意味で使われるポジショントークという言葉を使いましたが、あらゆる立場の人が、オープンな場でフラットな関係でポジショントークをすることが重要です。ポジショントークが問題になるのは、そのポジションを変えずに一つの考えに固執することです。相手のポジショントークを聞き、自分のポジションを柔軟に変えながら、解決策を作り出していく。この解決策を、スティーブン・R.コヴィーの言葉を使って「第三の案」と述べました。
医療の問題は、既得権益もからんで、立場の異なる人達が厳しく対立している問題も多いです。そんな状況を変えたいと思って本書を書きました。
是非皆さんも、本書を手に取り、医療の問題について考えてみてください。そして考えをTwitterやFacebook、LINEでもいいですが、SNSなどで発信してみてください。
本書が皆さんにとって、医療の問題を考えるきっかけになると同時に、医療の問題がよりよい方向に解決されていくことを心より願っています。」

1971年横浜生まれ。東京大学理学部卒業後、大学院で生物学の研究をしていたが、研究を医療に役立てたいと思い神戸大学医学部に学士編入学。
2004年、32歳で医師免許取得。新臨床研修制度の一期生として2年間を過ごし、研修修了後病理医になる。
06年、医学部在学中の研究により博士号(医学)取得。現在近畿大学医学部講師。
病理専門医、細胞診専門医。著書は『博士漂流時代「余った博士」はどうなるか?』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、科学ジャーナリスト賞2011受賞)、『わたしの病気は何ですか? 病理診断科への招待』(岩波書店)等。