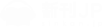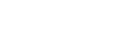ー運命を動かせ
- 定価:
- 1,500円+税
- ISBN-10:
- 4908059020
- ISBN-13:
- 978-4908059025
■常識外れだった吉田松陰 そのスゴさとは?
――吉田松陰は29歳のときに安政の大獄に連座して斬首刑にされます。若くして亡くなった松陰ですが、『超訳 吉田松陰語録―運命を動かせ』を読むと、松陰自体は「死」に対する恐怖感がなく、むしろそちらに向かって動いているようにも思えました。この松陰の言動の意味は一体どういうことなのでしょうか。
齋藤さん(以下敬称略):彼はあまり「死」を恐れていなかったと思います。むしろ必要であれば「死」も受け入れる姿勢をとっていた。なぜなら、大事なことは自分の存在ではなく、自分の志だからです。自分がなすべきことを果たしたら、あとは淡々と死を待つ。そんな気持ちだったのだと思います。
自分の志を受け継ぐ「同志」たちが出てくる。自分が撒いた種がどんどん芽を出す。そうすれば、自分は何も恥じることはないと考えていたのかもしれません。
――なるほど。
齋藤:実は、品川弥二郎宛の書簡で彼は三度死を覚悟したことがある、人はなかなか自分を殺してくれないと書いています。死ぬ間際までいったことがあるけれど、死ぬことができなかった。最期は斬首刑となりましたが、どんな失敗をしようが、なかなか簡単には死なないんです。ましてや、幕末の混乱の時代。それでも自分は捕まるが死刑にはならない。
今の時代で考えてみると、犯罪はともかくとして、ちょっとやそっとの失敗で命を奪われることはまずありませんよね。だから、失敗を恐れて何もできなくなる人は多いですが、「命まで取られるわけじゃない」とつぶやいてみるといいと思います。死ぬわけじゃない、ビビるな、と。
――松陰に言葉からは自分の「死」を次につなげようとする意識が見えます。
齋藤:彼の意識の中には、常に「死」があったと思います。ただ、松陰にとって「死」は終わりではなかった。自分の「死」を起爆剤にしようとしていたところがあります。
これは「野村和作宛書簡」につづられていますが、自分が捨て駒となって死んでみせることで、同志たちの決起を促しているんです。日本人があまりにも臆病になっている。門下生だった高杉晋作や久坂玄瑞も行動しない。ならば、と自分の「死」をもって同志を目覚めさせようとした。
――そう考えると、松陰は非常に常識外れな人間というか…。
齋藤:そう見えてしまいますよね。ただ、彼が自分自身のことを「狂人」と言っているのは面白い。成功者や社会を変えた人間は得てしてこういう人が多いと思います。周囲からは「絶対にやめたほうがいい」と言われても、それを成し遂げてしまう。
経営者の言うことが嫌だと思っても、それを誰も言えず、全員が保身に走った結果、結局経営が傾いたという会社はよくあります。松陰はそこで経営者に一言物申すタイプですね。自分の地位がどうなろうと、「それは違う」と言ってしまう。
何かが大きく変わるとき、だいたい松陰のような人間があらわれて、疎まれながらも一気に変えていくものです。ただ、現代の実社会でそれを実践するのは難しいかもしれません。だから周囲に自分の意見を聞いてもらえる環境をつくることは大事だと思います。
■本は一万冊を読むべし! 吉田松陰の「読書のススメ」
――本書は私たちの仕事の場面でも教訓になる言葉が多くありました。
齋藤:仕事というテーマでいえば、「講孟余話」の中で松陰が書いているのですが、適度に仕事があることで心に張りが出ますよね。もちろん多すぎてもいけないけれど、逆に仕事がないというのもストレスになる。一流の人はかなりの仕事量を抱え込んでいるけれど、みんな楽しそうに仕事をしています。それが理想的だと思います。
また、先ほども少し出てきましたが、日本人は失敗を怖がっているところがあります。でも、松陰は失敗を笑い飛ばすんですよ。安政元年にペリー艦隊が横浜に到着したとき、金子という同志と一緒に密航を企てるんです。ところがそれを失敗してしまう。金子は「なんてついていないんだ!」と悔しがるのですが、松陰は失敗を笑うんです。彼は失敗が逆に志を強くすると思っていたんですね。失敗をしたり、苦しかったりするときは落ち込んだ顔をしないといけないように思いますが、松陰に倣って笑ってみてはどうだろう、と。
――そのエピソードは本書の中でも印象的でしたね。
齋藤:また、日本人は交渉が下手だということは今でもよく言われますが、実は松陰がもう150年も前から指摘しています。交渉もせずに幕府が日米和親条約を結んでしまってから、その不平等条約が後々まで日本を苦しめることになるのですが、このときの日本は相手に譲ることだけを考えて、こちらの利を考えなかったんです。松陰はそんな幕府を「腰抜武士」と言っています(笑)。その条件ならば、こちらの条件も呑んでもらわないといけないというような交渉をしないといけなかったのだと思います。
――NHK大河ドラマの「花燃ゆ」は吉田松陰の妹である文が主人公ですが、吉田松陰の家族観はどのようなものだったのですか?
齋藤:これは「妹千代宛書簡」から垣間見ることができます。そこでは3つのことを大事にしていると書いてあって、一つは先祖を尊ぶこと、次に神様を拝むこと、そして家族や親類と仲良くするということです。
当時は親族がたくさんいて、兄弟が多いのは普通なこと。松陰も兄と弟が一人ずつ、そして妹が4人いました(一人は早世)。また、兄弟が多いということは、従兄弟も多いんですね。だから兄弟姉妹や親類と仲良くやることが大事だと述べています。
「妹千代宛書簡」では子どもの育て方が書かれているのですが、この中で松陰は「見習いて」という言葉を使っているんですね。これは、子どもは何を教えなくても、親を見て習って育っていくという意味なのです。現代は共働きも普通ですから、子どもが親の姿を見習う機会が少なくなってきているように思います。だから、この松陰の言葉は何かハッとさせられるところがありますよね。
――齋藤さんは吉田松陰のどのような部分に共感を覚えたのでしょうか。
齋藤:本書の「国を思わない日はない」というところに書いているのですが、私は小学生のとき、日本は資源がない中でやっていかないといけない国であると学んでから、この国のことを考えない日がなくなりました。自分のことよりも、日本の行く先を案じて心が暗くなるときがあります。日本を良くすることを考えて勉強をするものだと思っていたのですが、日本の未来を考えていない人が少なくなっているように感じます。
でも、幕末から明治維新にかけてのあの時代、松陰をはじめ、たくさんの人が日本の行く先を案じていました。そこに強い共感を覚えましたね。彼らのエネルギーが日本をアジアで初めて近代化させたわけですが、今は個人主義で連帯も弱く、エネルギーが集まりにくい状況にあります。
現代の日本の教育では、“日本のため”という意識を持たせにくいと思います。海外に目を向けることは大事ですが、松陰のように“日本のため”という意識を常に持つことが必要です。海外で道を切り開いてきた人たちはきっとそういう想いを持っていたのではないかと感じますね。
――では最後に、読書についてのお話をお聞きしたいと思います。本書では「一万冊の本を読破せよ」と書かれていますが、一万冊とは膨大な量ですね…。

齋藤:松陰は「万巻の書」という言葉で表現しています。要はたくさんの本を読まなければ、まともな仕事はできない、と。意味合い的には「たくさんの本」ですが、「万巻」の文字通り「一万冊」と受け取っていいでしょう。そのくらい本を読みなさいと言っているんです。
松陰は読書による鍛錬をすすめているわけですが、当時は本を読み、知識や教養を深めることは当たり前でした。ところが今は情報が重要視されて、知識や教養は軽視される傾向にあります。私は知識や教養は非常に重要だと思っていますし、「とりあえず松陰も言っているのだから一万冊の読書にチャレンジしてみよう」とこの本で書いているわけですね。でも最初から一万冊はかなり難しいと思うので、まずは百冊、そして千冊という感じで読んでいくといいと思いますよ。
(了)
- 1章
- 志を燃やす
―私欲を超えて公欲に生きろ! - 2章
- 迷いを断つ
―義を貫き、やると決めたらやる
- 3章
- 覚悟を決める
―できるまであきらめるな! - 4章
- 心を磨く・ワザを磨く
― 一進心不乱に学べ! - 5章
- 人を育てる・動かす・つながる
―熱い絆の人間関係を作れ!
齋藤孝(さいとうたかし)
1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学大学院教育学研究科博士課程等を経て、明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。主な受賞作品に1998年宮沢賢治賞奨励賞を受賞した『宮沢賢治という身体』(世織書房)、新潮学芸賞を受賞した『身体感覚を取り戻す』(NHKブックス)、シリーズ260万部を記録し、毎日出版文化賞特別賞も受賞した『声に出して読みたい日本語』(草思社)などがある。NHK Eテレ『にほんごであそぼ』の総合指導もつとめる。

- 定価:
- 1,500円+税
- ISBN-10:
- 4908059020
- ISBN-13:
- 978-4908059025