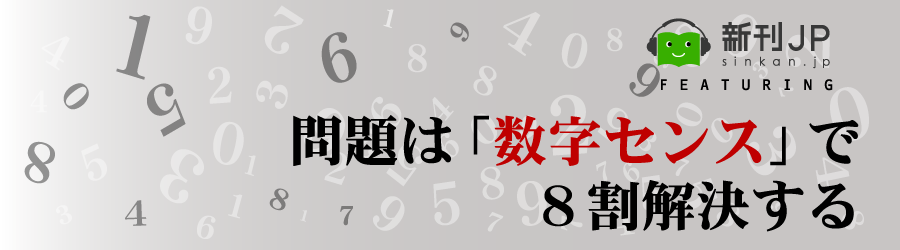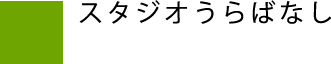今回は『問題は「数字センス」で8割解決する』の著者である望月実さんにお越しいただきました。今日は宜しくお願いします。
望月
宜しくお願いします!
矢島
早速ですが、この本の中で望月さんは「数字を読むことが大切だ」とか「数字で解決することが大切だ」と言っているんですが、実際こうした「数字センス」というものを身に付けるために、僕ら普通のサラリーマンは日常的にどんなトレーニングをすればいいのでしょうか。
望月
例えば、先日、卵の値段が10%値上がりしたというニュースが流れたんですが、そのあとに主婦の方がインタビューに「卵が値上げするなんてすごく嫌ですね」と答えていました。
私だったら「卵が10%値上がりして嫌だな」だけで終わらずに、実際に、いくら高くなるかを考えます。10個300円の卵の値段が10%上がったら、10個で330円になるので、30円上がるわけですね。もし、月30個卵を食べるのであれば、月に90円値上がりすることになります。
矢島
そうですね。トータルで考えると900円から990円に上がりますね。
望月
卵が10%値上がりしたと漠然と捉えるよりも、卵の値上がりが我が家の家計に与える影響は月90円だというところまで数字に落とせば、クリアになりますよね。
矢島
なるほど。10%上がるのは嫌だといったけども、月で見れば90円くらいですね。
望月
ですよね。値上がりっていくら値上がるかが大事じゃないですか。
矢島
確かにそうです。
望月
値上がりの額が月90円か、それとも900円なのかによって大分違います。でも、ほとんどの方は、そこまで数字に落とさないんですよね。
矢島
そうですね。では、そういう風に日常的なトレーニングとしては、値上がりと言われても、実際に数字に落として考えてみれば分かりやすいですよ、と。
望月
そうです。例えば、電気代にしても「面倒くさいな」「嫌だな」で終わっちゃうんじゃなくて、実際事務所の電気代いくらあがるか、とかを考えるんですね。
参考 東京電力プレスリリース 平成20年7~9月分電気料金の燃料費調整について
http://www.tepco.co.jp/cc/press/08042802-j.html
矢島
なるほど。電気を付けっぱなしにしておくと、いくら上がっちゃうんだろうっていうことですね。それは身近です。で、1つ気になっていた点があるんですが、最近、原油の値上がりがよく言われているじゃないですか。本の中にもそのエピソードが書いてありましたけど、原油の値上がりについて例えば望月さんならどのように考えますか?
望月
原油価格が40ドルから90ドルに上がったとすると、世の中でどんなことが起きると思いますか?
矢島
うーん。差し引き50ドルですよね。ガソリン代が高くなるので車を使わなくなる、そんな感じがしますね。
望月
そうですよね。原油が上がるとガソリンや電気代が上がって、損をするイメージがありますよね。でも値段が上がるということは、誰かが損してる一方で、誰かが得しているんですよね。例えば今回の問題ですと、日本にいる私たちは損をしますが、原油を売っている中東とかロシアの産油国が儲かりますよね。もしくは原油を輸入している商社が儲かるとかですね。事実、三菱商事は最高益になりましたし。
矢島
あ、そうだったんですか! 知らなかった。
望月
という風にですね、自分が損したら誰が得をしているのか、その裏を見に行く。これはそんなに難しい話ではないんですよ。自分が得したら損した人を探せばいいし。
営業なら「原油価格が値上がりして嫌だ」って言っているだけじゃなくて、中東とかロシアに対するビジネスを考えるとか、商社に営業かけに行くというような行動を起こすべきです。 数字が動くということはお金の流れが変わるということなので、何処にお金が流れているかをきちっと見定めて、そこにアタックかけることがビジネスの鉄則です。
矢島
確かに経営者じゃなくても、一般の人でも最近は株なんか簡単に買えますから、ロシアとか中東の株を買うというのはありですね。
望月
そうですね。
矢島
なるほど。普段から値上がりしましたとかそういったものを数字に落とし込んでみる。
望月
そうです。値上がりしたときに、誰が得するかを見るんですね。
矢島
で、次の質問にいきたいんですけども、この本は『問題は数字センスで8割解決する』というタイトルの通り、数字センスを磨きましょうという内容なんですが、やはり、この本を書かれたきっかけとして望月さんの周りに数字センスがあまりなかったり、数字が苦手な人が多かったんですか?
望月
そうですね。数字は…苦手というより嫌いな方が多かったですね。
矢島
嫌いまでいっちゃうんですか(笑)
望月
あんまり見たくないって方が多かったです。数字って嫌いじゃなければ普通に見て、だんだん力つけていくんですけど、大体の人は見たがらないんですよね。そこでブロックかかって、それ以上数字に強くなれないんです。
だから、私が書いている本やセミナーとかでは、出来るだけ数字を使わずに、数字の裏にある考え方を中心に説明していくようにしています。そうすると、「今まで数字が苦手だ」「つまんない」「わからない」って思っていた方々が「結構数字って面白いんだ」という風に感じていただいて、実際に使われるようになります。
私のセミナーに参加された方で「望月さんのセミナーで教わった通り数字を使ったら、プレゼンが上手く行きました」というコメントを頂きました。だから、数字の苦手な人の苦手意識をなくしたいんですよね。。
矢島
セミナーに来場する方は女性が多いと聞いたんですが、それは何故なんですが?
望月
女性の方は2割くらいなので多いというわけではありませんが、確実に女性のほうが盛り上がっていますね(笑)。
矢島
盛り上がっている(笑)。それは何故だと思いますか?
望月
「日経新聞に出てくる数字はこう読む」というようなセミナーでは、GDPの読み方などを勉強すると思いますが、GDPなんて普段の生活では使わないのでイメージがわかないですよね。私のセミナーや書籍では、身近な数字を使って説明してますので、イメージが湧きやすいんだと思います。
矢島
例えば普段使うような数字って、どんな数字を使われています?
望月
この本の中で例を上げると、「三越と伊勢丹の利益の差は200億円ありますが、この200億円の差は現場の数字で考えるとどうなるでしょうか?」というようなものがあります。
矢島
その章は面白かったですね。あ、そんなもんなんだって思っちゃいました。
望月
ほとんどの方は「三越と伊勢丹の利益の差は200億円あります」で終わってしまい、現場の商品の値段をいくら上げれば追いつくか、というところまでは考えないですよね。だから、私が大きな数字を目に見えるところまで分解して、それをどう考えるかって説明すると、皆さん「数字ってこんなに面白いんだ」って感じてくださいますね。
矢島
なるほど。GDPとかいった遠い数字を必死で覚えようとする人が多いと思いますけど、そうではなくて、末端価格はいくらかみたいな身近な数字に落とすことが、数字センスを鍛えるポイントなんですね。
望月
そうです。基本的に数字センスって、目に見えるところまで落とさないとつかないんですよ。身近な数字というのは立場によって変わってきます。例えばシンクタンクに務めていればGDPとかは身近な数字ですよね。でも、普通の人にとってはGDPは身近な数字ではありませんよね。
矢島
そうですよね。普通の人が公園で会って「今日はいい天気ですね。GDPも上がりましたね」とか会話しませんからね(笑)
望月
(笑)そうですね。身近じゃない数字をいくら勉強しても、数字に強くなるのは難しいと思います。
矢島
例えば、セミナー参加者の雰囲気が変わってきたら、参加者によって、また身近な数字を使ってみるのもありですよね。会計士の資格を持った人しか入れないセミナーだったら、最初からGDPって話をしても、「なるほど」って分かるわけですからね。
じゃあ、この本のポイントは身近な数字で考えてみる、と。さらに数字自体も使わずに基本的に仕組みとかを考えるということですね。
望月
そうですね。数字に強い人はたくさんの数字を一度に見ようとせずに、この数字はどういう仕組みで出来ているのかを考えてから見るんですよね。考えなら数字を見る癖をつけると、数字の面白さが分かってきます。
矢島
では、最後にこの『問題は「数字センス」で8割解決する』をこれから読もうと思っている方、もう読んでいる方はメッセージをお願いします。
望月
私がこの本で伝えたいのは、数字と上手くつきあう方法です。数字は信じすぎてもいけないと思いますし、嫌いだから見ないというのも違うと思います。数字は考えたり、伝えたりするときの便利な道具になりますので、この本を読んで、仕事に使える数字センスを身につけてください。
矢島
ありがとうございました!
今回、新刊JPとKinocastに登場して下さった望月実さん。
新刊JPスタッフがKinocast収録後のスタジオにお邪魔し、望月さんがその人生の中で影響を受けた漫画・映画をチラリと聞いてきました。
すると、意外にも望月さんが影響を受けた漫画は現在も連載中の、あの大長編漫画だったりと…?
楽しそうにお話をする望月さんに、スタッフも話を聞いていてとても楽しそうな表情。その後も談義に花を咲かせていました。「数字を身近に感じる」ならぬ「望月さんを身近に感じる」1コマです。
―これまで望月さんの人生に影響を受けた漫画や映画、ここはあえてそちらに限定させていただきたいんですが、そういうのはありますか?
望月「そうですね…。あ、森川ジョージさんの『はじめの一歩』は影響を受けていますね。大学生の頃かな、すごく読んでいたんですよ」
―そうなんですか!ブックナビゲーターの矢島さんも確か好きでしたよね、『はじめの一歩』
矢島「はい!僕も大好きです(笑)」
望月「あ、そうなんですか!」
―どういうところに魅力を感じますか?
望月「孤独に耐えながら頑張るっていう登場人物の姿にとても励まされましたね」
―『はじめの一歩』って今でも連載中で、しかも長編ですよね。全巻揃えていたんですか?
望月「揃えてはいました。ただ、一度処分してしまっているので、今はないんです(苦笑)。でも、すごく好きなエピソードが載っている巻は処分せずに今でも大事に持っていますよ」
―他にはどんな漫画や映画に影響されました?
望月「あとは、西山優里子さんの『Harlem Beat』というバスケットボール漫画も好きでしたね。これも大学生の頃かな。この中の澤村正博って登場人物がね、一匹狼として生きていく姿がすごくかっこいいんですよ。
あと、一番影響受けているという意味では映画の『ロッキー4』ですね。これは中学生、高校生のときに初めて観て以来、ずっと好きです。この主人公もね、孤独に耐えながら頑張っていくんですよ」
―そういった「孤独に耐えながら頑張っていく」という姿勢が好きなんですね(笑)
望月「そうですね(笑)。でも、そういう孤独に頑張る姿勢のキャラクターが好きだったからこそ、公認会計士の試験も頑張れたんだと思いますよ。とても励みになりました」
―でも、この話を聞いて望月さんがすごく身近に感じました。ありがとうございました!
望月「ありがとうございました」