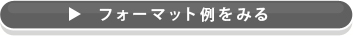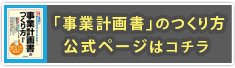―本書『51の質問に答えるだけですぐできる 「事業計画書」のつくり方』についてですが、今回このような内容の本を書こうと思った理由を教えていただけますか。
原 「私の会計事務所では、税金のことだけでなくお金にまつわる全てのご相談に乗りたいと思っていて、会社を作る段階から、儲かるシステム作りや、中期的な経営計画のつくり方などのご相談にも乗っています。
中にはなかなか事業が軌道に乗らないといいますか、アイデアはいいのに事業としてものにできない人が多いんです。そういう方々は何がいけないのかというと、数字や情報、データに基づいた地に足のついた事業計画が作れていないんです。
一方で、事業計画書について書かれた本はたくさんありますが、それを元に事業をすると本当に儲かる事業計画書の作り方を書いている本がないんですよ。大抵、そういう本は形式的なマーケティング理論や、利益計画をつくるためのテクニックについて書いてあるだけで、起業したばかりの人が、中期的なビジョンや、ビジネスのグランドデザインが描けるような具体的な事業計画書の作り方を書いた本はないんです。それが一番の理由ですね。
アイデアだけ思い浮かんで“これはいける!”と思って起業する人は多いですけど、クロージングができないんですよね。せっかく起業するんですから、きちんと儲かるようなビジネスをやっていけるお手伝いをしたいと思ったんです」
―今おっしゃっていたような、「アイデアだけの状態で起業をする方」というのは、実際にビジネスを始めた時にどういったところで行き詰ってしまいますか?
原 「まず、売り上げが立ちません。そういう方は、たとえば従業員を一人雇ったら売り上げが100万円立つとか、ここにお店を作ったらお客さんがたくさん来ると考えてしまいがちなのですが、それだけでは売り上げが立たないです。売り上げが立たないということはお金が入ってこないから、あっという間に資金が底をついてしまいます」
―それと、事業計画書がしっかりしていないと、融資ですとか投資を受けるところでも困ってしまいますよね。
原 「融資を受けられないのは問題ですけど、そもそも事業活動って、売上げをあげて儲けたお金を、再投資するという流れが基本ですよね。銀行から融資を受けられたとしても、そのお金を元手に儲けていかないと借りたお金を返せません。事業計画書がしっかりしていない人には、起業してからお金を儲けるまでの因果関係がつくれない人が多いです。
お店を開いたから、とういだけで、お客さんが来る訳ではありません。「お店のオープン」と「お客さまから購入していただく」との間のロジックが抜けてしまっているんです」
―本書は事業計画書に関する51問の質問とその解説でなりたっていますが、これらの質問の中には、実際に原さんが顧客の方々に聞く質問もありますか。
原 「そうですね。事業計画書って自分で作れない方が多いんです。事業計画書は融資を受ける時には絶対必要なので、弊事務所では、お客様方に代わって作成するサービスもあります。
この本には、その時にヒアリングする内容が全部入っています。ヒアリングの過程で、その方の想いや考えていることがわかるので、代わりに事業計画書を作ることができるんです。だから読者の方も、同じように質問に答えていけば事業計画書を作れるはずです」
―事業計画書をきちんと錬ることのメリットを教えてください。
原 「すばらしいビジネスのアイデアが思い浮かんだとしても、それはその人の頭の中にしかないので、誰も見ることができません。事業の成功はどれだけ多くの人を巻き込めるかにかかっています。お客様や株主や銀行、VC、従業員、みんなが同じ方向を向いていることが大事です。事業を興す時、みんな自分は世の中をこういう風に変えたいという想いがあるはずなんです。事業計画書はその想いを見える化するツールです。事業計画書があってはじめて第三者の共感を得ることができます。それが最大のメリットです」
―本書の内容のうち、原さんがもっとも重要だと考えていることを3つほど教えていただけますか。
原 「私は事業計画のスタートとして「事業コンセプト」をあげています。「事業コンセプト」というのは言ってみれば、こういう世の中にしたいという起業家の「想い」です。
そして、自分が興した事業の結果として、世の中をどのように変えたいか、という「ビジョン」が事業計画のゴールになります。さらに、それを実現するためには、どこの戦場で戦うべきかという「ドメイン(戦略)」を選ばなければなりません。この3つのどれが欠けても、事業は成功しません。これが一つ目のポイントです。
ビジネスはお金を儲けてなんぼです。ビジネスモデルの中のどこにキャッシュポイントを仕掛るか、いかにお金を儲ける仕組みをつくるか、これが二つ目のポイントです。
この二つを押さえることで事業計画はかなり明確になります。三つ目はそれをいかに継続するか、ということです。「ブルーオーシャン」戦略とは、“自分ができることで、お客さんが望んでいることで、競合他社がやっていないこと”を見つけることをいいます。資金力のない中小企業にとって、優れた戦略ですが、ブルーオーシャンは長続きはしません。せっかくブルーオーシャンを見つけても、あっという間に競合他社が参入してきますから。その戦場はあっという間に、「レッドオーシャン」になってしまいます。
その時「レッドオーシャン」でも勝ち続けられるあなたの強みは何ですか、ということになる。それが三つ目のポイントですね
」
―事業計画書において、個人的に一番の難関は、「ロードマップ」(事業のシュミレーション・数値による裏付け)の箇所かと思ったのですが、現実的なシュミレーションをする時に気をつけなければいけないことはどのようなところでしょうか。
原 「とにかく調べることです。一番難しいのは売り上げ予測です。経費の予測は自分に主導権があるので簡単にできますが、売上に関しては、商品を買うか買わないかの決定権はお客様が持っているので、予測が難しいです。そこをいかに予測するかがポイントです。そのためには、とにかく調査。お店を出すなら実際に現地に行って周辺の土地を調べたり、周りの人に聞く。できるだけ沢山のデータを集めて、データに基づいて売上げの予測を立て、そこからさらに8掛ぐらいにします。そこを端折ったらダメです。どんなに素晴らしいプランを考えてもそこが抜けている人が多いんですよ。事業計画書をつくるとき、手を抜かずに時間をかけて欲しい箇所ですね」
―事業計画書を作る際の落とし穴はどんなところにありますか?
原 「誰でも、銀行や第三者によく見せたいと思うのが普通ですよね。そこで利益がプラスになるような見栄えのいい計画書を作ってしまうことです。今申し上げたように、売上げって地道に調べてヒアリングをして、このくらいならいけるというのを調べないといけません。銀行や上司によく見せたいから、というだけで黒字になるように利益から逆算して売上げの数字を作ってしまいがちです。そうすると事業計画書は破綻してしまいます」
―事業の構想を練る時に想定すべきリスクをいくつか教えていただければと思います。
原 「政治の方向性や経済の状況、社会が何を求めているかなど、世の中のマインドですね。法律で禁止される予定の商品を、ビジネスにしようとしてもダメですから。たとえば、本書では、世の中が安全な食材を求めている。でも人々の舌はこえているので、やっぱり美味しいものが食べたいんです。そういう世の中の動きに敏感になっておかないといけません。起業する人は、自分が提供したい商品のことで頭がいっぱいになっていて、回りが見えていない方も多いです。
あと、マーケットが拡大しているのか縮小しているのか、自分の戦うマーケットの現況はチェックしておかないといけません。縮小しているマーケットにイノベーションを入れたら独り勝ちになる可能性もあるので、縮小しているマーケットがいけないというわけではありません。けれど、縮小しているマーケットに拡大しているマーケットの戦略を持ち込んでもうまくいくわけがありませんよね
」
―本書は起業を考えている方に向けて書かれたものかと思いますが、そういった方々以外に、どのような人に役立つとお考えですか?
原 「イメージしたのは従業員500人くらいまでの、中規模の会社の経営企画室にいる人たちです。新しい事業のアイデアを考えて、企画を立てる方だとか、そういう方々ですね。だから、起業をしなくても役に立つ本だと思います。
また、既存の事業の業績が良くないということで、新しく事業を起こして事業再生を目指す方にも役立つと思います」
―本書の強みはどんなところにあるとお考えですか?
原 「事業計画書の作り方がわかる本、事業計画書が書ける本はこれまでにあったのですが、ビジネスを拡大させられる事業計画書を作れる本は、今はまだこの本しかないと思います。質問に答えていけばいいので、マーケティング・会計などの専門知識もいりません。少なくとも、本の中にビジネスモデルのサンプルとして出てくる事業の計画書レベルのものは作れるはずです」
―最後になりますが、起業を考えている人へメッセージをお願いします。
原 「人間、何が起きるかわかりません。自分が勤めている会社が安泰ということもありませんし、今事業がうまくいっていても、急に風向きが変わって売れなくなるかもしれません。でも自分が世の中をどういう風に変えたいという思いがきちんとわかっていれば、そうなってもブレないと思うんです。
私たちは同業他社が安い値段でやっているからうちも下げるとか、売れなくなったら値段を下げるという価格競争に巻き込まれがちです。だけど自分のやりたいことがはっきりしていれば、安易な値下げにも走らなくてすみます。
目の前に自分がやりたいこととは別のおいしそうなビジネスが転がっていた時、安易に手を出すと失敗するんですよ。自分がやりたいことは何か、それが実現した時、世の中はどう変わっているのかというビジョンを、しっかり持ってほしいです。日本は資源の少ない国ですし、震災があったことでみんな自分に対する自信を失っているように見えます。だから、起業を通じてみんなが自信を取り戻せるようになってほしいですね。これは私の壮大な妄想ですが(笑)
」


 東京外国語大学英米語学科卒業。スタッフ20名全員が女性だけの、「原&アカウンティング・パートナーズ」を主宰。
東京外国語大学英米語学科卒業。スタッフ20名全員が女性だけの、「原&アカウンティング・パートナーズ」を主宰。全日本答練(TAC主催)で、「財務諸表論」「法人税法」を全国1位の成績で税理士試験に合格。一部上場企業の子会社や外資系企業から中小企業まで幅広いクライアントをもち、企業会計の現場に強い。
税理士会では税務支援部長を経験し、中小企業は節税よりも財務力を強化すべきとの思いから、事業計画書の作成など地に足のついた経営支援を通じて、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。
慶應義塾大学大学院の税理士補佐人講座、日税連の地方公共団体外部監査人講座修了。
「小さな会社のための総務・経理の仕事がわかる本」、「個人事業者のための会社のつくり方がよくわかる本」ソーテック社刊