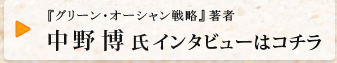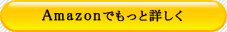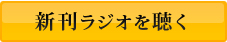
―「恩」を次の世代につなぐ経営実学
著者名: 中野 博
出版社: 東洋経済新報社
定価: 1,680円
ISBN-10: 4492532854
ISBN-13: 978-4492532850
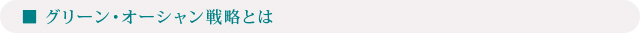
・社会貢献。環境保全、貧困問題の解決などのCSR活動を前提とする新しい経営戦略のことを指す。
・「地球および自然」「企業の成長と利益」「人間の幸せ」のトリレンマをいかに解決するか?そして売り手、買い手、世間、地球の「四方よし!」こそがこれからの経営と説く。
・知恵と工夫をこらしながら、美しい大自然の恵みを、次の代へ美しいまま残す。そうした努力を多くの仲間や、企業、NPOなど協力し、本気で取り組むことこそがこの「グリーン・オーシャン戦略」の神髄。
【著者・中野博さんによる、3つの定義】
1、自然の恵みに感謝して、節約または代替可能なものはできる限り早期に対策を講じて、限りある地球の資源を有効活用する。自然を守るとともに、企業や個人の力で未来への恩送りとして、積極的に森を育てるなど「自然を育むこと」を実践し、自然と共存共栄していくことをミッションとする。
2、未来に起こりうる可能性をさまざまな角度から予測し、最悪のシナリオまでリスクを計算し、企業または個人としてできうる限りのリスクの削減に努める。ここでいうリスクとは、因果関係が明らかに認められる場合を指すだけでなく、人間および地球環境への影響が可能性として考えられることも含む。「疑わしきは製造しない、使用しない、売らない」という姿勢が重要である。
3、企業は使用している自然の恵みや地球の資源、エネルギーなどの活用について包み隠さずに情報公開を行い、消費者とともに愛情を持って、持続可能なモノづくりやサービスを推進する。この情報公開により多くのステークホルダーとともに、「人と地球にやさしい」社会を作ることを企業活動および個人のライフスタイルの根幹とする。
 CSRは正式名称「Corporate Social Responsibility」といい、日本語では「企業の社会的責任」となる。企業が営利活動をするなかで地域社会にも貢献を果たしたり、環境問題に配慮したりしながら、持続可能な社会を形成するための一助を担うということを理念としている。
CSRは正式名称「Corporate Social Responsibility」といい、日本語では「企業の社会的責任」となる。企業が営利活動をするなかで地域社会にも貢献を果たしたり、環境問題に配慮したりしながら、持続可能な社会を形成するための一助を担うということを理念としている。そこに込められた思想は、企業も市民社会の一翼を担っているというものである。例えば公害など、利益の追求が結果的に未来の子どもたちに虐待を与える結果を引き起こしてしまうことを問題とし、企業が社会に対して責任を持った行動を求められているのだ。
つまり、企業が活動できるのは、その地域があるからこそであり、豊かな環境があるからこそであり、「今が良ければそれでよい」「今、儲けられればそれで良い」という考え方から脱し、持続的に人々と企業が共存できるような社会を作り上げようということである。
今であれば、やはり東京電力の原子力発電所の問題はCSRを考える上で欠かせないだろう。
原子力発電は日本の経済活動にとって大切なものであった。
しかし、現在のような状況になると、それは恩恵と共に大きな代償を伴うものでもあったということは誰もが認識したところだろう。福島第一原発から半径20キロメートル圏内は封鎖され、関係者以外誰も入れなくなった現実があるのであり、今後いつまでこのような状況が続くか、その見通しすら立たない。
環境は静かに破壊され、一時的にではあるが、そこに人は住めなくなった。
「持続可能な社会」の意味を、私たちは改めて知ったのである。
地球の環境を使ってモノを製造してきた企業が、地球規模で環境の変化が起きているなかで、環境に対しての働きかけを行う。それは至極当然のことではないか。アメリカでは、CSRを実践していない企業はその地域からそっぽ向かれるという話もあるという(日系企業がアメリカに進出して壁に当たってしまうのは、この概念をしっかりと理解している企業が少ないからであるという理由もあるそうだ)
本書はイケア、デル、キューセルズ、トヨタ自動車、パナソニック、鹿島建設、積水ハウス、サントリー、ANAグループなど、様々な大企業のCSRの事例が掲載されていて、CSRを意識した経営が現代においていかに必要か、そしてどのようにすればそういった経営が可能であるのかを説く。
危機管理能力のなさが露呈した東京電力の二の舞になってはならない。今こそ、CSRが求められているのである。
(新刊JP編集部)