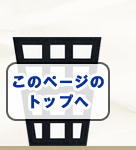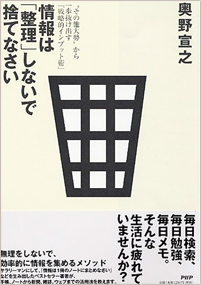著作家。1981年、大阪府生まれ。大阪府在住。同志社大学文学部社会学科を卒業後、出版社および新聞社への勤務を経て、現在、フリーランスの文筆家。作家のエージェント、(株)アップルシードエージェンシーにスカウトされ2008年、『情報は1冊のノートにまとめなさい』(ナナ・コーポレート・コミュニケーション)でデビュー。31万部のベストセラーになり、続編の『読書は1冊のノートにまとめなさい』(同)、『だから、新書を読みなさい』(サンマーク出版)と合わせて累計部数は48万部を超える(2009年12月現在)。
ジャーナリスト出身なので、情報の整理や収集、伝達、読み取り、加工などのノウハウは豊富。そのほか、読書術、発想法、仕事術、デジタルツール、文章作成、ウェブ活用にも詳しい。著作のほか、ビジネス記事の執筆、書評、エッセイ、インタビューなど実績を活かして、単行本、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、講演会へと、活動の場を広げている。おもしろくて、読者の役に立つ、実用的なものを書くことを信条にしている。
既婚。辛党。カレーなど辛いものには目がない。趣味は、切手・スタンプ収集、辞書収集、博物館めぐり、自転車に乗ることなど。
- 序章 大事なのは「情報の入口戦略」
- 「本当になんでも書くの?」
- 入口で選別すれば「整理」はいらない
- あなたにとって本当に重要な情報は、案外少ない
- 四段階からなる「戦略的インプット」
- 第1章 捨てる勇気を持とう
―「普通じゃないアウトプット」―のために - 奥野 宣之の一日
- 「できる人」との差は「捨てることができるか」で決まる
- 「みんなと同じ」は泥の船
- 「違い」はインプットから始まる
- その場で処理する「瞬間芸」が今の時代には必要
- 情報に流されていると「独自性を失う」
- 特別な情報なんていらない
- 情報に序列を付けることが重要
- 戦略的インプットは頭の中を「寄せ鍋」にする
- 戦略的インプットは「行動」のこと
- 四段階で情報を手なずける
- 第2章 情報を見逃さない力を身につける
- 目をつくっておくとすべて取材現場になる
- ゴールに「必要なもの」をリストアップ
- リマインダ―で意識にすり込む
- 第3章 捨ててはいけない情報にアクセスする技術
- なんでもつまんでみる原則
- ウェブでは「まとめサイト」を探す
- 情報に「いちいち引っかかる」技術
- 「辞書引き」を癖にする方法
- 横と縦の軸で散らす
- 情報のいちばん「おいしい」食べ方
- 理想は「触れると同時に捨てる」
- 第4章 「使える情報」「捨てる情報」を即決するルール
- どんな情報も「ただの人間」が作っている
- 情報は小さなブロックに分解できる
- 判断基準①:新旧
- まず化石化した情報を探せ
- 劣化するなら新鮮なうちに
- 判断基準②:正確性
- 固まっていないセメントに乗るな
- ウラを取ってある情報には乗れる
- 判断基準③:加工度
- 一次情報は圧倒的に強い
- 二次情報からは他者の視点を得る
- 判断基準④:発信源
- 権威は媚びずに利用する
- 発言の動機、発言者のメリットを読む
- 判断基準⑤:希少性
- 「また来る情報」は捨てる
- どこででも聞ける話はいらない
- 判断基準⑥:再現性
- 原本以外はさっさと捨てる
- 再入手が可能なら捨てる
- 自分の考えは一期一会の情報
- 判断基準⑦:効率性
- 知ってる情報に取り合わない
- 広がる「メタ情報」を集めよう
- シンボル情報は確実に獲る
- 判断基準⑧:インパクト
- そのメディアの「名物」はとりあえず食べる
- サプライズこそ醍醐味
- 判断基準⑨:コスト
- 自分に合わないならあきらめる
- 処理コストが高いものはあきらめる
- 扱いやすければ拾う
- 第5章 情報の捨て方、拾い方
- 調べものは「辞書」から
- フリーソフトでウィキペディアもオフライン化
- 「まとめ記事」で勉強する
- 何度も読む本はまとめておく
- 書類はコピー用紙の箱にどんどん捨てる
- 通信社のウェブサイトで速報チェック
- 月刊誌の「遅さ」を活用する
- 「政府」を情報ソースにする
- プレスリリースを手に入れる
- ウェブで「現場」に行く
- 数字と固有名詞から拾う
- 日経の名物情報は「企業ニュース」
- 一般紙の名物情報は「わかりやすい説明」
- 辞書を引いたら「未知」だけメモ
- 書類に「×」を書く
- 「自分由来」は必ずメモする
- 酒の席の発言は隠れてメモする
- 夕刊に注目する
- 願望はメモして冷静になる
- 街の観察日記を書く
- 打ち合わせの雰囲気をメモに残す
- 偶然の出会いはメモる
- 会議情報は一元化しておく
- 捨てる資料はその場で廃封筒に
- テレビは録画ベースで観る
- 映画を観たらメモを作る
- 説明用DVDはメモ化して捨てる
- 自分の考えを検閲しない
- 現物の保存には手書きがいい
- イベントでは「現物」を採取
- 「複数販売」で情報を多様化
- 最後には自分で考えることが必要
- あとがき