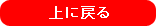ゆとり世代の「説明力不足」を叩き直す ≪第三回≫
今年新入社員で会社に入った皆さんはきっと四苦八苦している頃だろう
そう、「説明」の大変さに。
報告・連絡・相談、つまり「ホウレンソウ」が重要とされるビジネスシーンにおいて、 「説明力」はその3つと並んで求められるスキルだ。
新刊JP編集部にも新人・吉男が入ってきた。記事の執筆スピードは速く、目の付けどころもかなり独特。編集部メンバーが持っていなかった分野の知識にも長けている。ただ1点、「説明力」がないのだ。
これはものすごく損なこと。
素晴らしいアイデアも、相手にキチンと伝わらなければ採用してはもらえない。
第1回目では企画会議の様子をお伝えしたが、ここでは「主語・述語がはっきりしていない」 「助詞・接続詞が正しく使われていない」という問題が露呈された

実は文章をちゃんと書くことは、わかりやすい説明をするうえで、とても重要なことなのだ。 しかし編集部の指摘もあり、文章力は向上。企画会議もスムーズにいった。
第2回目では街頭インタビューを決行。
街頭インタビューでは、相手からいつどのようなことを質問されるかわからない。
そこで上手く説明をするために、「相手の質問を理解すること」「話を適正化すること」を学んだ。

そして吉男育成計画の第3回目。
今回は「電話取材」
に挑戦してもらうことになった。
われわれ新刊JP編集部では常套手段の電話取材。
だが、相手の表情が読めないし、例えば相手が理解できていないときに紙に図を書いて説明することもできない。
実は声と言葉だけで話すのは、かなりの説明力が求められるといえる。
というわけでさっそく金井を相手に試しにやってみることに。

知っている人にかけているということもあり、落ち着きを見せる吉男。いい感じだ。というか、目の前にいるしな…。
では、一通り出来たところで、実際に取材をしてみよう。
今回は、とある出版社に書籍の売れ行きとその反響について聞いてみることになった。
プルプルプル・・・

電話「はい、○○出版ですー」
吉男「あ、え、も、もしもし。私、新刊JP編集部の吉男と申します」
電話「いつもお世話になっておりますー」
一瞬どもったが、ここまでは順調。
吉男「あのー、えっと、新刊JPで掲載するニュース記事で、取材をしていまして、お電話をかけたのですが・・・はい」
うーん、ちょっと惜しい。やっぱり少し不明瞭。
結局、説明に時間をかけてなんとか担当者に電話を回してもらえたが、緊張しているせいなのか、取り次いでもらうまでに時間がかかってしまった。そのうえ、担当者は不在だった。
こんなときは『言いたいことがキチンと伝わる説明力の基本』(工藤昌幸、松井寿夫/著、こう書房/刊)で勉強をしなければ。
◆説明が上手くいくPoint 5:「結論」を意識しよう
まず、説明をするときは「結論」を最初に伝えてしまうと良い。
今回の電話取材でいえば、こちら側が一番伝えたいのは「○○という本について取材を行いたい」ということだ。
先にこれを伝えたうえで、その結論に至った理由や経緯、補足情報を付け足す。
ここで重要なのは、「相手が答えやすいように」を説明することだ。
「新刊JPに掲載するニュース記事の件で、取材をしていまして」だと、
相手は「ああ、そうですか」という返答しか出来なくなる。
「○○という本について取材を行いたい」「担当者につないでほしい」など、
結論を明確にすることで、相手も「どんな内容ですか?」「でしたら担当に回します」と、
必要な回答をしやすくなるのだ。
手順としては以下が最もわかりやすくなる。
結論→結論に至った経緯・理由→結論
この型さえ覚えてしまえば、電話取材の申し込みも楽になるぞ、吉男!
◆説明が上手くいくPoint 6:5W1Hを意識しよう
5W1Hといえば、説明の基本中の基本である。
5W・・・Who(誰)、What(何)、Where(どこ)、When(いつ)、Why(なぜ)
1H・・・How(どのように)
これがちゃんと盛り込まれていないと、相手に意図が伝わりにくくなってしまうのだ。
今回の電話取材の場合だと、
When・・・今
Why・・・『○○』という本が売れているので
Who・・・担当編集の方に
Where/How・・・電話インタビューで
What・・・どのような反響が来ているか聞かせてほしい
こう当てはまることになる。おお、スッキリしている。すごい。
頭の中がこんがらがってしまっている場合は、こうして5W1Hに当てはめて考えてみると整理される。
というわけで、これらの反省を踏まえて2件目の電話取材。

プルプルプル・・・
電話「はい、○○出版ですー。」
吉男「あ、○○出版様でいらっしゃいますか? 私、新刊JP編集部の吉男と申します・・・」
電話取材の申し込みは成功。
ここまで来れば、あとは担当者に用意された質問をぶつけるだけになる。
まあ、本当に不安なら説明する段階から台本を用意すれば良かったんだろうけど!
ここ最近で、吉男の「説明」する力は格段に飛躍してきた。 これも『言いたいことがキチンと伝わる説明力の基本』のおかげだ。
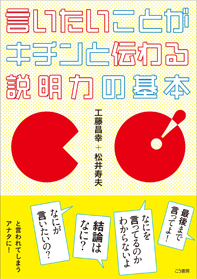
ちなみに、第3章では結論や5W1Hを意識することのほかに、「ナンバリング」「ラベリング」といった具体的なテクニックが紹介されており、それを鍛えるトレーニングをすることができる。
まさに説明力の基本が学べる1冊!
説明力が上がれば、あなたの株もグッと上向くはずだ。
また、あなたの周りに説明がヘタだったり、説明に自信がない新入社員、もしくは2年目3年目の若手社員がいる場合は、本書をすすめてみてはどうだろうか。
彼・彼女の説明力が上がることで、彼らもあなたもずっと仕事がしやすくなるだろう。
(新刊JP編集部)

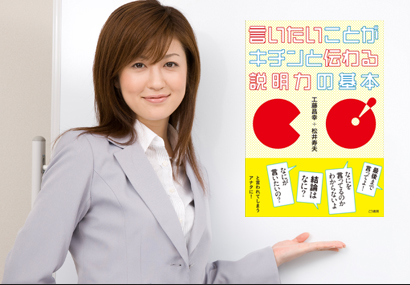
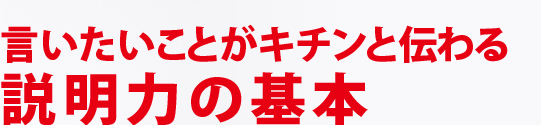
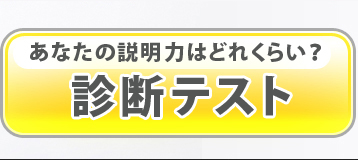

![[企画]ゆとり世代の「説明力不足」を叩き直す](../_images/special/description/title_project.png)