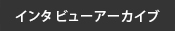『学校の近くの家』著者 青木淳悟さん
「泣かせる小説ならこの作家」「ミステリーならこの人」などなど、小説にはタイプによって代表的な作家がいるものだが、お題が「ヘンな小説」であれば、真っ先に名前が挙がるのが青木淳悟だろう。
青木さんの最新作『学校の近くの家』では、杉田一善(小学5年生)の目から見た学校、友達、親、先生、地域が書かれるが、そこには冒険も事件もファンタジーもない。
ただ、もちろん「単なる日常」でもない。そもそも小学生の目を通せば「単なる日常」などというものは存在しないのだ。
出版界の最重要人物にフォーカスする『ベストセラーズインタビュー』。第78回は青木淳悟さんの登場だ。
interview index
前代未聞の「小学生小説」はドラマを避ける
― 『学校の近くの家』は主に小学5年生の杉田一善の視点で語られます。私は昭和56年生まれの一善とほぼ同世代なので、読んで単純にすごく懐かしかったのと、小学生当時は言葉にしようと思っていなかった日常風景が活字になるとこれほど新鮮なのかという驚きを感じました。まずは、今回「小学生」を題材にした理由を教えていただけますか?

青木:
担当編集者と「次は青春小説を書きたい」ということを話していて、当初は「主人公は中高生」と考えていました。
でも、ある時に村田沙耶香さんの『マウス』という、小学5年生の女の子を主人公にした小説を読んで、小学校の教室の風景だとか日常の描き方に非常に影響されまして、自分も小学生を書きたいと思ったんです。村田さんは女の子なので、僕は男の子バージョンでやってみようと。
― 舞台は青木さんご自身が育った狭山市になっていますね。
青木:
そうですね。だから、自分が長い時間を過ごした場所を書く「ふるさと小説」という一面もあると思います。
最初は、主人公が通う小学校を創作するのではなく、自分が実際に過ごした小学校を書きたいという気持ちがあって、そのつもりで書こうとしたのですが、自分と作品との距離が近すぎてすごく書きにくかったんです。
そこで、隣の学区にある出身中学を小学校に見立てて書き始めた。ややこしい話ですけど、そうしたらうまく書けるようになりました。
その中学校がすごく辺ぴなところにありまして、すぐ脇が自衛隊の基地で、近くに西武新宿線の線路が走っていて、畑が広がっていて、という感じでした。そして、小説の中の一善の家と同じように、学校のすぐ近くに家が建っていて、通学路が通っている。僕自身も中学時代はいつもその家を見ながら通学していたのですが、通っている学校がこんなに近かったらどんな気持ちがするのかとちょっと不思議だったんです。
― 今少しお話に出ましたが、一善の家の学校との近さについては作中で何度も書かれていましたね。
青木:
「どん詰まりの道が正門前から延びてグラウンドの向かいの道にぶつかるT字路を左に折れてすぐ右側の路地」という設定なのですが、ちょっと説明がゆき過ぎた気もしています。
家の位置は重要だということで何度も繰り返したのですが、雑誌に連載している時だったらそれでいいにしても、本にまとめるとなるとまた違うじゃないですか。担当編集者から「また家の位置が説明されていますけど、これでいいんですか?」と聞かれて、聞かれると僕も大丈夫なのか不安になるという(笑)。
物語という物語がほとんどない話なので、「核」になったのは、「学校の近くに家がある」というその位置関係のちょっとした奇妙さでした。僕自身は住宅街の中にある家で育って、普通に登校班になって通学していたんですけど、そこまで学校に近いところに住んでいる子がどんなふうに感じているのか想像がつかないところがあります。今回書評していただいた松田青子さんは、「学校が嫌いだから、学校のすぐそばに住みたかった」ということを書かれていましたが、それもまた意外でおもしろい。作中で一善は登校班での通学を免除されて一人で行き帰りするんですよね。自分ではなくても、現実にそういう友達がいたら、「家が近くて楽そう」とか「うらやましい」と感じる子も多いだろうし、意外とこの「近さ」への思いというものを共通体験として持っているんじゃないかと思いました。教室の窓からその友達の家が見えて、洗濯物を干しているお母さんと目が合ってしまう、というような。
― たしかに、学年に一人くらいは学校の隣に家があるような子がいました(笑)。ところで、「小学5年生」というのは微妙な年齢ですよね。低学年のような幼さはないにしても、中学生が視野に入ってくるほどでもない。
青木: 大きくもなく小さくもないという不安定な年齢なのかもしれません。この小説を書くにあたっても、6年生だと最上級生ということで、「卒業式」や「修学旅行」など小学校生活を総括する感じになってしまい、「ドラマ」の要素が入ってきてしまうので避けたんです。
― 「ドラマ」は避けるんですか?
青木: 避けますね……(笑)。
― 確かにいわゆる学校生活のイベントが出てきませんね。
青木:
そうですね。でも、書いている僕自身、そういうイベントの記憶が全然ないんですよね。参加していたはずなのに。
唯一覚えているのが小学校6年生くらいの時に、何かで時代劇をやったことなのですが、「『多勢に無勢』でござりまする!」っていう自分のセリフだけははっきり覚えていて、これは小説の中に書きました。
ただ、劇自体はどんなものだったか覚えていないんですよ。たしか織田信長が主人公で、彼が死ぬまでを劇にしたものだったと思いますが、なぜ小学生の劇にそんな渋いセリフを、と思いますよね。
「“子どもならではの恐怖心”の部分を広げていけたらなと思っていた」
― ご自身よりかなり若い「小学生」の視点で小説を書くにあたって、心がけたことはありますか?

青木:
本当は自分自身の小学生時代に重ね合わせるように書こうと思っていたのですが、いつの間にかずれていってしまって、最後には年齢までずれて主人公が昭和56年生まれということになってしまいました。
なぜこんなことになったのかというと、作中で「東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件」という、宮崎勤の事件を取り上げたのですが、話の都合上、その事件は一善が小学校低学年の時期に起こったということにしたんです。それで年齢が僕自身と少しずれてしまった。
― はっきりとした影響というよりは、一善の生活の端々にそれとなく事件の影が落ちているという雰囲気が印象的でした。
青木:
隣町で被害者が出たりしていたので、それなりに衝撃的で、今でも覚えています。自分のふるさとをじっくり書きたかったので、当時のことで覚えていることは総動員しようと思っていたのですが、いざ思い出そうとすると全然思い出せなくて小説にする材料が足りていない状態でした。
だから、覚えているささいなことを膨らませていく形で書いていったのですが、書いているうちに思い出してくることが結構あって、それは楽しい経験でしたね。
― 一善以外の登場人物も普通なようでいてどこか独特ですよね。個人的には5年生の担任教師の「馬淵先生」の訓辞めいた挨拶が好きです。おそらくどんな先生も新学期は似たような挨拶をするはずなのですが、それが文字になると不思議と笑えます。
青木: ありがとうございます。先生のセリフは自分でも書いていて楽しかったです。普通なのにどこかヘンだぞというセリフが多かったと思います。また物語がない分、作中人物の言動に負荷をかける感じで、不安定さというか不穏さを出したかったですね。
― そして一善の両親は、人間くさいお父さんと、風変わりで少々エキセントリックにも見えるお母さんが対照的で目を引きました。
青木:
母親は家の象徴というか、家庭を代表する人物として書いています。
学校と積極的にかかわろうとしたり、逆に距離をとろうとしたりする、ある意味アクの強いキャラクターですね。
― 「物語がない」ということをおっしゃっていましたが、確かに物語の時間が小学5年生の新学期からあまり進みません。
青木:
そうですね、基本的には小学5年生の一善が「2年生の時はこうだった」「3年生の時は……」というように過去をくよくよ思い出すところが多いです。
成人してから小学生時代を思い返すというのはわかりますが、小学生なのに過去を振り返ってばかりの男の子が主人公の作品というのはあまりないだろうし、そこが微妙でおもしろいんじゃないかと思いました。
― その主人公の性質をよくあらわしているのが、第6話目の「11年間の思い出」というタイトルですね。
青木: 12年間だと「小学校生活のまとめ」といった感じで区切りがいいですけど、そこを「11年」とすることで、まとまりにくい感じを出せたかなと思います。一善が書いた「5年生になって感じたこと」という作文にまつわるお話なのですが、自分でも結構気に入っています。
― 一善が先生の挨拶から膨らませた妄想の描写が続いて、普通ならそこから本筋に戻るところを戻らないというのも青木さんらしいと思いました。そもそも「本筋がない」といった方がいいのかもしれませんが。
青木: ひょっとしたら学校と一善の母親は対立しているのかな?と匂わせて物語が発展する要素を出しておきつつ、それを回収していなかったりもします(笑)。
― お母さんが急に怒り出したり、不穏なところがありますよね。
青木:
そうですね。きちんと書けたかどうかはわからないのですが、そういう母親の不可解な様子だったり、いつのまにか家の隣に学童保育所ができていたりといったエピソードを書くうえで根底にあったのは、子どもならではの恐怖心だったんだと思います。
今思い出そうとしてもはっきりとは思い出せないのですが、当時「怖れの感情」を日常的に抱いていたことは覚えています。それは僕の性格的なものもあったと思いますが、それを差し引いても大人より子どもの方が恐れを抱くことは多いはずです。そういう「子どもならではの恐怖心」の部分を広げていけたらなと思っていました。
「大江文体」を目指して書かれた小説を誤って消去…

― この作品もそうですが、お話に「筋」を作らないということが青木さんの小説では徹底されている気がします。これはご自身のスタイルとして意識されていることなのでしょうか。
青木:
ある時間の経過を書く時に、今書いた場面と時間的につながっている続きの場面を書きたくないとか、同じ場面が続かないように短く終えるとか、そういう「書き方」レベルでの好みはありますね。
今回の小説は連作短編で、一つ一つの話が必ずしもつながっている必要はなかったので、それならむしろ「本筋」を作るのではなく「ズレ」ていた方がいいなと思っていました。
ただ、それで予定していた6編を書き終えても「終わった感」がまったくなかったので、本になるタイミングで6編目の「11年間の思い出」を加筆したのに加えて、7編目を書き下ろして追加したんです。そうすれば何とかまとまるかなと。
全体の内容として、本当に何事もなく学校の近くにあいかわらず住み続けて、一善も成長していません。だから、最初に考えた「青春小説」の要件を何も達成していないんですよ。
― 「成長」とか「友情」のような、一般的な青春小説の要件を避けているようにも感じられます。
青木: 正面から青春小説を書くのはちょっと分が悪いというか……(笑)。
― そんなことはないですよ!しかし、「青木淳悟=ヘンな小説を書く作家」という評価は定着しています。ご自身で「ヘンな小説」を書いている実感はありますか?
青木: 「スキマ産業」的に書いているなとは感じています。ジャンルというものがあるとすると、そこからちょっと外れるものを、とは思っていますね。それが書きやすいですし、これからもそういうものを書いていきたいです。
― そうした作風のルーツはどこにあるのでしょうか。
青木:
「ルーツ」といえるのかはわかりませんが、大学1年生の時に大江健三郎さんの小説が好きで読んでいて、「大江文体」を目指して小説を書いたことがありました。
思えばそこが「小説を書く」ということのスタート地点だったのですが、それから海外文学や日本の現代文学の作品を読みながら少しずつ吸収していったんじゃないかと思います。
― 大江文体を目指すというのは楽しそうですね。
青木: 小説を書くこと自体はじめてでしたから、書くこと自体への感動もあって結構スピーディに書けたんですよ。1カ月で100枚くらい書いて、それを「新潮新人賞」に送ろうと思っていたんですけど、送る前日に原稿のデータをまちがえて消してしまったんです。
― それはショックですね。もしかしたらそれがデビュー作になっていたかもしれないのに。
青木:
いや、受賞するかどうかでいえば全然問題にならないような小説だったと思います。ただ、そこから急に書けなくなってしまって、大学2年、3年はほとんど何も書けませんでした。
当時、自分に似た主人公をつくって、身近な日常を書くということをやっていたのですが、生産性がないというか、短編を3つか4つ書いたくらいで壁にぶつかっていましたね。それもあって4年生くらいから書き始めた『四十日と四十夜のメルヘン』では、自分からちょっと離れたものを書こうとしていて、結果的にそれがデビュー作になりました。
作品の出来と関係あるかはわかりませんが、その頃は就職活動もせず、「自分はこれからどうするんだろう」という不安もあって尻に火がついた感じでしたね。そこでようやく「小説は何をやってもいいんだ、どう書いてもいいんだ」という心境になれた気がします。
― その『四十日と四十夜のメルヘン』が新潮新人賞を受賞してデビューされました。書いた時の手ごたえとしてはどうだったんですか?
青木:
全然手ごたえはなくて、雑誌に掲載される選考の途中経過も見ていませんでした。ダメだろうと思って次の作品を書いていましたから。
でも、最終選考のひと月くらい前に編集者から電話がかかってきて、最終候補に残っていることを知ったという感じです。
今回の加筆もそうなのですが、僕は「修正魔」みたいなところがあって、原稿を直したくなってしまうんですよ。『四十日と四十夜のメルヘン』は単行本になる時と文庫になる時でそれぞれ結構直していて、3バージョンくらい世に出ているのですが、実は厳密に言うと最終選考の前にも直して差し替えてもらったので、実際にはもっとたくさんあります。
― 青木さんが人生で影響を受けた本がありましたら、3冊ほどご紹介いただければと思います。
青木:
まず中学生のころ司馬遼太郎にどっぷりと浸り込んでいて、将来は時代小説作家になりたいと思っていたんです。司馬ファンとして1冊だけ選ぶのはなかなか難しいところですが、忍者小説の『梟の城』(新潮文庫)が忘れがたい。これがデビュー作で直木賞を取っていますが、ちょっと読み返そうかと思って本を開いたら面白すぎて読みやめられない。いきなりこんなプロフェッショナルな仕事をしているなんてスゴすぎて、夢を諦めてよかったなと思います(笑)。
2冊目がスティーヴン・キングの『トウモロコシ畑の子供たち』(扶桑社ミステリー)。これは久しく絶版になっていると思いますが、高校時代に出会いました。スリラーというのかモダン・ホラーというのか、またエンターテインメントの完成度の高さにやられてしまうわけですが、密度の濃い傑作ばかりの短篇集です。「英米文学」より先にこういうものを読んでいたことを思い出しました。絶版なのが本当に疑問で、超オススメです。
3冊目はデビュー直前に読んだ福永武彦訳『現代語訳 古事記』(河出文庫)です。まず率直に、古事記が読めるということに驚きました。こんなに楽しい神話があるのを教えてくれないなんて、学校教育は何をしているんだと文句をいいたい。大学受験では日本史が一番得意でよく勉強していたのに。国語でも社会でも古事記は必修にしないと、と思うくらい感動しました。僕のデビュー一作目の「クレーターのほとりで」という作品は古事記に触発されて書いたんです。
― 小説の世界で独自の立ち位置を築いている青木さんですが、今後の目標がありましたら教えていただけますか。
青木: 今のところ著作が少なくて、平均すると年に1冊いかないくらいなので、もっとコンスタントに単行本を出していきたいです。小説でとりあえずは生活できているので、これからも何とか書き続けていきたいと思います。
― ちなみに、「もっと売れたい!」というような欲はありますか?
青木: それはあるのですが、売れる要素がなくて(笑)。売れるきっかけになるとしたら芥川賞とかになると思うので、いつか取れればいいなとは思っています。芥川賞は「新人賞」なので、僕にいつまでその資格があるかはわかりませんが。
― 最後になりますが、青木さんの小説の読者の方々にメッセージをいただければと思います。

青木: 今回は「小学生小説」ということで書き始めましたが、これまでにない小学校を描けたのではないかと思っています。忘れてしまっているかもしれない小学生時代のことを思い出しながら読んでいただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
取材後記
デビュー以来、風変わりな小説を書き続ける青木さんということでお話を理解できるかどうか不安でしたが、インタビューではとてもわかりやすく作品の成り立ちを語ってくださいました。
『学校の近くの家』は、小説を読み慣れている人ほど頭の中が「?」だらけになってしまうかも。でも、主人公・一善の視点に慣れてくると、彼の目を通して見るいきいきと驚きに満ちた世界に魅了されるはずです。
(インタビュー・記事/山田洋介、写真/金井元貴)
青木淳悟さんが選ぶ3冊

- 『梟の城』
- 著者: 司馬 遼太郎
- 出版社: 新潮社
- 価格: 840円+税
- ISBN-10: 4101152012
- ISBN-13: 978-4101152011
- Amazonでみる

- 『トウモロコシ畑の子供たち』
- 著者: スティーヴン キング (著), 高畠 文夫 (翻訳)
- 出版社: 扶桑社ミステリー
- ISBN-10: 4594003206
- ISBN-13: 978-4594003203
- Amazonでみる

- 『現代語訳 古事記』
- 著者: 福永 武彦 (編集)
- 出版社: 河出書房
- 価格: 840円+税
- ISBN-10: 4309406998
- ISBN-13: 978-4309406992
- Amazonでみる
プロフィール
■ 青木淳悟さん
1979年埼玉県生まれ。2003年「四十日と四十夜のメルヘン」で新潮新人賞を受賞してデビュー。 2005年、同作を収めた作品集『四十日と四十夜のメルヘン』で野間文芸新人賞を受賞。2012年『私のいない高校』で三島由紀夫賞受賞。他の著書に『いい子は家で』『このあいだ東京でね』『男一代之改革』『匿名芸術家』がある。(出版社サイトより)

- 『学校の近くの家』
- 著者: 青木 淳悟
- 出版社: 新潮社
- 定価: 1600円+税
- ISBN-10: 4104741043
- ISBN-13: 978-4104741045
- 出版社: 新潮社
作品紹介
先生たちのキャラクター。男子と女子の攻防。隣の学区への小さな旅。PTAと子ども会。行事をめぐる一喜一憂。父 との微妙な距離感。連続誘拐殺人事件の影。深まる母の謎――。小学生自身の視点で克明に立ち上がる、ノスタルジーも無垢も消失した、驚くべき世界像! 三 島賞作家による、スーパーリアルな「小学生小説」。(出版社サイトより)
■インタビューアーカイブ■

第81回 住野よるさん
第80回 高野秀行さん
第79回 三崎亜記さん
第78回 青木淳悟さん
第77回 絲山秋子さん
第76回 月村了衛さん
第75回 川村元気さん
第74回 斎藤惇夫さん
第73回 姜尚中さん
第72回 葉室麟さん
第71回 上野誠さん
第70回 馳星周さん
第69回 小野正嗣さん
第68回 堤未果さん
第67回 田中慎弥さん
第66回 山田真哉さん
第65回 唯川恵さん
第64回 上田岳弘さん
第63回 平野啓一郎さん
第62回 坂口恭平さん
第61回 山田宗樹さん
第60回 中村航さん
第59回 和田竜さん
第58回 田中兆子さん
第57回 湊かなえさん
第56回 小山田浩子さん
第55回 藤岡陽子さん
第54回 沢村凛さん
第53回 京極夏彦さん
第52回 ヒクソン グレイシーさん
第51回 近藤史恵さん
第50回 三田紀房さん
第49回 窪美澄さん
第48回 宮内悠介さん
第47回 種村有菜さん
第46回 福岡伸一さん
第45回 池井戸潤さん
第44回 あざの耕平さん
第43回 綿矢りささん
第42回 穂村弘さん,山田航さん
第41回 夢枕 獏さん
第40回 古川 日出男さん
第39回 クリス 岡崎さん
第38回 西崎 憲さん
第37回 諏訪 哲史さん
第36回 三上 延さん
第35回 吉田 修一さん
第34回 仁木 英之さん
第33回 樋口 有介さん
第32回 乾 ルカさん
第31回 高野 和明さん
第30回 北村 薫さん
第29回 平山 夢明さん
第28回 美月 あきこさん
第27回 桜庭 一樹さん
第26回 宮下 奈都さん
第25回 藤田 宜永さん
第24回 佐々木 常夫さん
第23回 宮部 みゆきさん
第22回 道尾 秀介さん
第21回 渡辺 淳一さん
第20回 原田 マハさん
第19回 星野 智幸さん
第18回 中島京子さん
第17回 さいとう・たかをさん
第16回 武田双雲さん
第15回 斉藤英治さん
第14回 林望さん
第13回 三浦しをんさん
第12回 山本敏行さん
第11回 神永正博さん
第10回 岩崎夏海さん
第9回 明橋大二さん
第8回 白川博司さん
第7回 長谷川和廣さん
第6回 原紗央莉さん
第5回 本田直之さん
第4回 はまち。さん
第3回 川上徹也さん
第2回 石田衣良さん
第1回 池田千恵さん