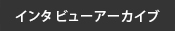第58回となる今回は、デビュー作「べしみ」を含む連作短編集『甘いお菓子は食べません』を刊行した、田中兆子さんが登場!
結婚、セックス、夫婦関係などなど、様々なことに悩み、苦しみながら生きる40代の女性たちを、時に哀しく、時にコミカルに描いたこの短編集は、女性なら誰でも他人事とは思えないはず。
今回は執筆時のエピソードや、込められた思いなど、この作品の裏側について語っていただきました。

■ 『甘いお菓子は食べません』に込められた意味

― いきなりですが『甘いお菓子は食べません』とはおもしろいタイトルですね。
田中: ありがとうございます。本の中の作品のどれかの名前を取って全体のタイトルにするというやり方もあるのでしょうが、そうではなく収録されている作品すべてに通底するタイトルをつけたかったんです。それでアイデアを出そうと各作品の共通点を探していたら、どの作品にも主人公がお菓子を食べている場面がないことに気がついたんです。
― 言われてみると、確かにそうですね。
田中:
お酒を飲む場面はあるんですけど、お菓子を食べる場面はないんですよ。それは単純に発見で、このことをタイトルにしてみたら、読み手の方々に色々な意味を持たせられるのではないかと思いました。
「甘いお菓子は食べません」というと、文字通りの意味にも取れますし、「“いつまでも若々しく”などという甘い言葉には騙されない」という意味にも読めます。また、「甘いお菓子を好むのは女性」という価値観を踏まえたうえで、「そういうものではないですよ」というニュアンスもありますよね。
― 心理描写や、主人公が内省する描写が多く、どれもとても切実だと思いました。この本で書かれている女性ならではの悩みや問題は、田中さんご自身のものとも重なるところがあるのでしょうか。
田中:
おそらく無意識の中には入っているんだと思いますが、それをそのまま作品にしたわけではありません。
この短編集には、結婚やセックス、出産などさまざまなことで悩む女性たちが出てくるのですが、どれも女性にとっては普遍的で切実な悩みです。こういった悩みによって追い込まれた精神状態に置かれた人はどう考えるのかということを、登場人物たちでシミュレーションする感じで書きました。
― 『甘いお菓子は食べません』は、田中さんのデビュー作である「べしみ」だけがある状態に、他の作品を加えていくことでできあがったということですが、書いていてどんなところに難しさを感じましたか?
田中: 短編集を作るにあたって「べしみ」を最初には持ってこないということだけは決めていました。結局最後に置いたのですが、そこまで辿りつけるのかな、という不安はありましたね。
― それぞれの作品同士で少しずつ接点がありますよね。それが最後の「べしみ」までうまくつながるのかという。
田中: そうです。そういう不安がありましたし、一つひとつの短編はどれも非常に苦労したのですが、今振り返ると「この作品で出てきたこの人を、こっちの作品では主人公にしよう」とか、作品同士をうまくつなげていくのはすごく楽しかったです。
― 「べしみ」は悲しくもどこか滑稽ですよね。主人公の女性器に奇妙な異変が起こるわけですが、その異変に驚くと同時に「起こってしまったことは仕方ない」と切り替えてしまうたくましさが可笑しかったです。
田中: これが20歳くらいの女性だったらものすごいショックを受けると思うんですけど、この主人公は40代ですからね、年齢を経た女性のたくましさというか(笑)。
― 同じく年齢を重ねていても、男性ではこうはいかないのでしょうね。
田中:
たとえばEDになった時ですよね。「べしみ」のように女性器に異変が起こるというのは、男性に置き換えるならEDになるようなものか、と人に聞いたことがあるのですが、その人いわく、男性がEDになるというのはそれどころではなく、もっと一大事だということでした。
「性」というものへの関わり方は、男性と女性でまったく違うんだなと思いましたね。「べしみ」の主人公のように、気持ちを切り替えられてしまうというのは女性ならではかもしれません。
― アルコール依存症の妻とその家族を描いた「残欠」もすばらしかったです。これは、かなり調べてから書かれたようですね。
田中:
そうですね、文献も読むのもそうですけど、アルコール依存症の方々のグループにお邪魔してお話を聞いたり、ということもしました。
それと、私自身はアルコール依存症ではないのですが、お酒は大好きで、ちょっと若い頃にものすごく飲んで記憶がなくなったことがあったんです。そういうこともあって、アルコール依存症についての興味だとか、他人事じゃないなという気持ちは以前からありました。
― アルコール依存症患者である主人公の心理が怖いほどリアルでした。彼女はアルコールを求めてしまう自分を極度に恐れているわけですが、そうやって「自分以外の何か」ではなく、「自分の中にある何か」に怯えて生活するのは精神的にものすごく辛いんだろうなと。
田中:
一番辛いのは、一生抱えていかないといけないことですよね。完治というのはないので。
やはり物語なので、どこかで結末を作らないといけないのですが、主人公の内面の戦いは一生続きます。その部分はちゃんと書かないといけないとは思っていました。
― また、主人公の夫のようなキャラクターは現代の男性に多いような気がします。非常に淡々としていて、困った時は助けてくれるけども本音を決して見せない。
田中: 人間的には非常に優しいんですよね。だけど、その優しさの方向が奥さん(主人公)にうまく伝わらない。「残欠」では、こんな夫婦が人間関係の一つの殻を破るまでを書きました。
■ 「小説演習」で最低点をつけられた大学時代
― この短編集を通じて、内面に食い込むような描写が特徴的でした。作風に影響を受けた作家さんはいらっしゃいますか?
田中:
単純に好きな作家さんということで言えば、古井由吉さんや金井美恵子さんなど、「何を書くか」ではなく「どう書くか」にこだわりを持っている作家さんが好きなのですが、それぞれに唯一無二の描写を持っていらっしゃるので、影響とか真似をするという次元ではありません。
ただ、「べしみ」を書いた時、富岡多恵子さんのことは少しだけ念頭にありました。作品そのものへの影響というよりは、富岡さんの書き手のナルシシズムに陥らない客観性にすごく惹かれているんです。自分もそういう作家でいたいと思いますね。
― 田中さんのプロフィールを見ると、8年間OLをされていて、現在は専業主婦とありますが、小説を書き始めたきっかけはどんなことだったのでしょうか?
田中:
専業主婦になった当時、お芝居がすごく好きでたくさん観ていたんです。歌舞伎も観ていましたし、小劇場に足を運んだりもしていました。それもあって、最初は戯曲を書いていたのですが、賞に応募しても全く引っ掛かりませんでした。
それが30代くらいで、40代になると、お芝居ってものすごい数の人を巻き込まないといけないし、若いうちじゃないと無理だな、と思い始めて、一人で完結させられる小説を書くようになりました。
― いつか書いてみたいというのは若い頃からあったのでしょうか。
田中: 大学の授業に「小説演習」というのがあって、全員小説を書くんですよ。その授業の先生が平岡篤頼さんといって、小川洋子さんや角田光代さんを育てられた方なのですが、その平岡先生に最低点をつけられてしまったんです。それで「ああ、もう私は書いちゃいけないんだな…」と(笑)。そういうことがあったので書きたいとは全然思っていませんでしたね。
― それは学生にはショックですよね。
田中: ショックといえばそうなんですけど、当時はヌーヴォー・ロマンだとか、高橋源一郎さんの作品だとか、筋のないものばかり読んでいて、頭でっかちだったんです。そんな時に書いたものですから、小説の体をなしてなかったと思うんですよ。その前は現代詩ばかり読んでいたので、物語を作るということができていなかったんです。だから、最低点で仕方なかったんじゃないかと今では思っています(笑)。
■ 谷川俊太郎を追いかけて現代詩の世界へ

― 小説演習の授業を受講するだけあって、かなりの読書家だったんですね。
田中:
でも、育った家には絵本や児童文学がまったくなかったんですよ。幼稚園などで多少読んだりはしているんでしょうけど、そういったものにはほとんど触れませんでした。
記憶にあるのが、幼児向け雑誌を買ってくれると言われたのに、「そんな子どもっぽいものは読みたくないから漫画にしてくれ」と言って「りぼん」とか「なかよし」を買ってもらっていたことです。それが幼稚園くらいでした。
小学校にあがってからは、父が買ってきた「週刊新潮」と、母が毎月取っていた「家庭画報」を読んでいましたから、子ども向けの本は読まずじまいでしたね。
― それはかなり変わった読書歴だと思います。
田中:
「週刊新潮」の中でも好きだったのが「黒い報告書」でしたから、いきなり下世話なものに入ってしまいました(笑)。図書館にも行っていましたが、読んでいたものは小説ではなくて、歴史などの本が多かったです。
だから文学的なものとなると、現代詩が最初だと思います。
― いきなり現代詩!
田中: 谷川俊太郎さんの詩が小学校の教科書に載っていたりするじゃないですか。そのプロフィールを見ていたら、著作のところに『二十億光年の孤独』とあって、そのタイトルにやられてしまった。「この人の詩は絶対わかる!」と直感して、そこから谷川さんを追いかけるように、現代詩を読み始めました。
― 中学生以降の読書はいかがですか?
田中: 「ぴあ」などを読んでいました。私は富山の田舎の出身なのですが、東京の情報が得られる雑誌を読むのが背伸びしたい中学生の流行りだったんです。
― 東京でやるコンサートの情報を富山で調べる中学生。
田中:
そうなんです(笑)。東京の情報を知ってるぞ、という自分が好きだったんでしょうね。
あとは、当時「ビックリハウス」っていうサブカルの雑誌があって、そういうのを読んだ男の子たちが自慢してくるんですよね。それに対抗するように「現代詩手帖」を読んだりとか。
だから、しっかり小説を読むようになったのは高校に入ってからですね。
― 大学の授業で最低点をもらってからは、小説を書く熱意は冷めてしまったのでしょうか。
田中:
そうですね。そこからはひたすら読むだけでした。大学を卒業して就職した会社では外回りの営業をしていたのですが、移動時間が長くてたくさん本が読めたんですよ。
移動中に本を読んで、読み終えた本を会社のロッカーに入れて、ということを繰り返していたら、辞める頃にはロッカーが本でぎっしりになっていて、段ボールに詰めて持ち帰った記憶があります。その頃にはもう何でも読んでいましたね。
― 田中さんが人生で影響を受けた本がありましたら、三冊ほどご紹介いただければと思います。
田中:
まずは『詩のこころを読む』です。「日本人なら一家に一冊」と言いたいほどの名著ですね。『甘いお菓子は食べません』にもちょっとだけ登場する金子光晴さんの「寂しさの歌」ですとか、日本を代表するすばらしい詩が平易な言葉で紹介されています。岩波ジュニア新書なのですが、大人が読んでもまったく問題のない、とてもいい本です。
二冊目は『描かれた女性たち―現代女性作家の短篇小説集』。これはアメリカの女性作家の作品を集めた短編集です。アン・ビーティが好きで買ったんですけど、他のラインナップも豪華なんですよ。先日ノーベル文学賞を受賞したアリス・マンローも、確かこの本で知ったんだと思います。
読んだのはもう25年くらい前なんですけど、当時はアメリカの女性作家たちがフェミニズムを経て、古くからある「男性を支える存在としての女性」とは違う女性を書き始めた時期だったんです。それがすごく新鮮だったのを覚えています。
最後は古井由吉さんの『小説家の帰還―古井由吉対談集』にします。どの対談も、一言一言が非常に深くて、きちんと読み取れているかはわからないのですが、小説を書くようになってからこの本のすごさがさらにわかったといいますか、示唆を受けています。たとえば、夏目漱石の『道草』はこんな読み方ができて、この表現はこう解釈できて、など、気づかされることが多いですね。
― 今後どんな作品を書いていきたいとお考えですか。
田中:
「小説新潮」で書かせていただいた短編が昨日校了になったのですが、それが「昭和の不器用な男と女のいい話」というような作品なんです。
これはもともと「いい話」を構想していたわけではなくて、編集の方のアドバイスを受けて、最終的にそういう話になったのですが、「自分にこんないい人の話が書けるんだ」という驚きがありました。自分では性格が悪い人の話を書くことばかりが得意だと思っていたので、しみじみとしたいい話も書けるというのは発見だったんです。
こんなことがあったものですから、色々なお題をいただいて、どんな作品でも挑戦してみたいという気持ちはあります。あまり自分のコアがなく、色々なものに影響されやすいところがあるので、その中でどこまでのものが出せるのか、やってみたいですね。
― 最後になりますが、読者の方々にメッセージをお願いします。
田中:
人によっては全然共感することのできない本かもしれません。でも、その共感しない部分を探して読んでいただけたらうれしいです。特に男性の方には「女ってそうなのか、男とは全然違うんだな」と思っていただけたらいいですね。今の女性をかなり意識して書いているので、2014年の女性はこうだというのがわかると思います。
■ 取材後記
「好きな本について嬉しそうに話す人に悪い人はいない」と常々思っているのですが、田中さんはまさにそんな方。もちろん、こういった方に取材をするのは楽しいもので、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
「色々なものに影響されやすい」と語ってくれた田中さんが、これからどんな人やものに影響されて、作品の中にどう現れるのか。次回作が早くも楽しみになるインタビューでした。
(インタビュー・記事/山田洋介)

■ 田中兆子さん
1964年富山県生まれ。8年間のOL生活を経て、現在は専業主婦。短編「べしみ」で、第10回「女による女のためのR-18文学賞」の大賞を受賞する。『甘いお菓子は食べません』がデビュー作。東京都在住。

あらすじ
アルコール依存から脱することのみを目的に生きる女。「きみとはもうセックスしたくない」と夫から宣言された女。母になるか否かを考え続ける女。もっと愛したい、もっともっと愛されたい、なのに――40代を漂う彼女たちが見つけた、すべて剥がれ落ちた果ての欲望の正体とは。女の危うさと哀しみを迫力の筆致であぶり出した、連作短編集。■インタビューアーカイブ■

第81回 住野よるさん
第80回 高野秀行さん
第79回 三崎亜記さん
第78回 青木淳悟さん
第77回 絲山秋子さん
第76回 月村了衛さん
第75回 川村元気さん
第74回 斎藤惇夫さん
第73回 姜尚中さん
第72回 葉室麟さん
第71回 上野誠さん
第70回 馳星周さん
第69回 小野正嗣さん
第68回 堤未果さん
第67回 田中慎弥さん
第66回 山田真哉さん
第65回 唯川恵さん
第64回 上田岳弘さん
第63回 平野啓一郎さん
第62回 坂口恭平さん
第61回 山田宗樹さん
第60回 中村航さん
第59回 和田竜さん
第58回 田中兆子さん
第57回 湊かなえさん
第56回 小山田浩子さん
第55回 藤岡陽子さん
第54回 沢村凛さん
第53回 京極夏彦さん
第52回 ヒクソン グレイシーさん
第51回 近藤史恵さん
第50回 三田紀房さん
第49回 窪美澄さん
第48回 宮内悠介さん
第47回 種村有菜さん
第46回 福岡伸一さん
第45回 池井戸潤さん
第44回 あざの耕平さん
第43回 綿矢りささん
第42回 穂村弘さん,山田航さん
第41回 夢枕 獏さん
第40回 古川 日出男さん
第39回 クリス 岡崎さん
第38回 西崎 憲さん
第37回 諏訪 哲史さん
第36回 三上 延さん
第35回 吉田 修一さん
第34回 仁木 英之さん
第33回 樋口 有介さん
第32回 乾 ルカさん
第31回 高野 和明さん
第30回 北村 薫さん
第29回 平山 夢明さん
第28回 美月 あきこさん
第27回 桜庭 一樹さん
第26回 宮下 奈都さん
第25回 藤田 宜永さん
第24回 佐々木 常夫さん
第23回 宮部 みゆきさん
第22回 道尾 秀介さん
第21回 渡辺 淳一さん
第20回 原田 マハさん
第19回 星野 智幸さん
第18回 中島京子さん
第17回 さいとう・たかをさん
第16回 武田双雲さん
第15回 斉藤英治さん
第14回 林望さん
第13回 三浦しをんさん
第12回 山本敏行さん
第11回 神永正博さん
第10回 岩崎夏海さん
第9回 明橋大二さん
第8回 白川博司さん
第7回 長谷川和廣さん
第6回 原紗央莉さん
第5回 本田直之さん
第4回 はまち。さん
第3回 川上徹也さん
第2回 石田衣良さん
第1回 池田千恵さん